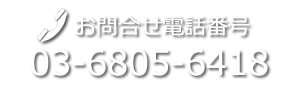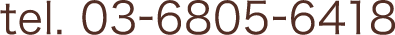自律神経失調症について その2
2019年11月13日 22:07更新
専門外来コラム
10/22の専門外来コラムの続きになっています。
2018年12月14日に出版となった拙書「最高のパフォーマンスを引き出す自律神経の整え方」から抜粋と一部手を加えての内容となっています。本の順番どおりではありません。
当院の自律神経失調症外来を受診される方は、下記のパターンに分かれています。
- 自律神経失調症と診断されたが、治療を受けても改善しない。
- 自分は、そこまで精神的にプレッシャーとかを感じていない。今の問題は、体調不良がメインだから、精神的な部分がメインではないのでは?
- 自律神経失調症と思ったから、受診された。
自律神経失調症は、不定愁訴(動悸、めまい、全身倦怠感+慢性疲労、息苦しさ・呼吸苦、喉のつまり・違和感、不眠・睡眠の乱れ、腹部の不調)などの原因が説明できないから診断名がついてしまっているのです。
実際に、血液検査、心電図、レントゲン、CTやMRI、超音波など、様々な検査では、それらの不調の原因が説明できないのです。
原因が見つからないとは言え、自律神経が乱れていたら出るような症状なのです。
私は、どの観点から自律神経を捉えているのでしょうか?
52P~60Pからの引用です。
最大の原因は「骨格」にあり
自律神経に影響を与えるさまざまな要因の中で、私が特に重視しているのは、「骨格」の乱れです。
「えっ、そんなものが影響しているの?」と思われたかもしれません。どういうことか、詳しくみていきましょう。
まず、「骨格」の乱れとはどういうことかというと、骨格が本来あるべき状態ではなくなっていることを指します。「骨格のゆがみ」と言ったほうがわかりやすいでしょうか。代表的な状態は、「姿勢の悪さ」です。 自律神経失調症で受診を希望される方々のほとんどは、姿勢が悪く、診察室に入ってきて数歩で、骨格のゆがみに気がつきます。
もちろん、ビジネスパーソンで受診される方も、同様に骨格のゆがみがすぐにわかることが多いです。ではなぜ、骨格がゆがんでいると自律神経は乱れてしまうのでしょうか?
まず、「脊髄」の問題があります。
自律神経は、脳の視床下部から始まり、「脊椎」の中の脊髄を通って、全身の各器官につながっています。
脊髄は脳と体をつないでいる神経の束であり〝首から腰までつながっているケーブル〟とたとえることができます。人が生きるために欠かせないとても重要なもので、これが損傷してしまうと、体を動かせなくなったり感覚がなくなったりしてしまいます。
脊髄は「脊椎」という骨のトンネル(背骨)を通っているおかげで、損傷から守られています。
脊椎のトンネルは、通常 S 字に近いカーブを保っています。これは脊髄をしっかり守り、人間の体を効率よく維持するために理想的なカーブです。
しかし、このカーブが変形したり、ずれてしまったりすると、中のケーブルは圧迫され、正常な働きをしづらくなってしまうのです。
さらに、「呼吸」の問題もあります。
骨格がゆがみ姿勢が悪くなっていると、肺がつぶされ、呼吸が浅く短くなってし まいます。
体に十分な酸素が行き渡らないことは、それだけで化学的ストレッサーによるストレス要因となります。また、浅く短い呼吸をしているときは交感神経が優位になっている状態です。
日常的に浅く短い呼吸をつづけていると、常に交感神経優位の状態になってしまい、自律神経のバランスが乱れる原因になってしまうのです。
ストレスが骨格の乱れに拍車をかける
「自律神経が乱れている」と言われると、多くの方は精神的なストレスのせいだと考えがちです。
しかし実際には、先に骨格がゆがんでいて、自律神経のバランスを失っている・失いかけている状態であると思ってください。
そこに、精神的ストレスや環境的ストレス、その他の身体的ストレスの問題が絡み合って、より自律神経の乱れがひどくなってしまうのです。
また、それらのストレスは、骨格の乱れにもさらに拍車をかけます。
たとえば、精神的なストレスが加わったとき、人間は自然と「歯を食いしばる」という習性があります。歯を食いしばると、顔の前方に強い力がかかるので、頭部が前に出やすくなります。頭部は安定した位置にないと、重力を強く受けてしまいます。すると、頭部を支えている首や肩は、前に出た分を支えないといけなくなり、余計な負担がかかります。
頭部の重さは体重の8〜 10 %近くもあります。体重が 60 キロだとすれば6キロです。そこにさらに重力が加わるのです。 前に出ると3倍近くの重さになると言われており、なんと 18 キロもの重さになってしまいます。
首・肩、脊椎のトンネルは、この重さに耐えなければいけません。短時間ならそこまで問題はないでしょうが、長時間続くと、トンネルにも限界がきてしまいます。
トンネルが耐えられなくなったら、中を通っている脊髄のケーブルも圧迫されてしまいます。そして、脊髄を通っている自律神経は、余計に乱れてしまうわけです。
「気づかない乱れ」が一番怖い
自律神経が乱れているという自覚や、姿勢が悪い(骨格がゆがんでいる)という自覚がある方は、まだ大丈夫です。3章ではゆがみを治すために気軽にできる方法をたくさん紹介していますので、これから治していきましょう。実は、一番怖いのは、自分の乱れに気づいていないことなのです。
電車の中の風景を思い浮かべてみてください。一車両にいる人たちの何%が、スマートフォンを使用しているでしょうか?
おそらく、およそ 80 %以上の方が使用しているのではないかと思います。
そのときの姿勢を思い出してください。下を向いている状態の方がほとんどだと思います。
下を向けば向くほど、脊椎のトンネルは頭の重さに耐えないといけなくなります。
人間がスマートフォンでネットやゲームを楽しんでいるあいだ、首や肩は文句も言わずに耐えているのです。そして、慢性的にその状態なので、首や肩がこっているということにすら気がついていないことが多いのです。
「気づかないくらいならいいじゃん」と思われるかもしれませんが、気づかないということは、決してよい状態ではありません。
実際に、自律神経の乱れで当院を受診される方で、首や肩、背中を触ってみるとすごくこっていて、すぐにでも治療すべき状態であるにもかかわらず、そのことに気づいていないことも多くあります。
①こりや痛みがない→②こりや痛みを感じる→③実際にこっているのに感じないか、触っていることすら感じない という段階を経ていきます。当院を受診される方々は②か③の方がほとんどです。
自律神経がひどく乱れている方は、③の状態がより強い傾向にあります。
現代人の9割は自律神経が乱れていることはすでに述べたとおりです。これはそのまま、現代人の9割は骨格がゆがんでいると言い換えてもよいです。パソコンやスマホの使用が日常的になった現代、ゆがみがまったくないほうが珍しいのです。
「自分は大丈夫」と思っている方も注意されてください。
また、「特になにもしていないのに、以前はひどかったこりを最近感じなくなった」という方や、マッサージなどに行って「すごくこっていますね」と驚かれるのに自覚がないような方は、特に要注意です。
↑までが本からの引用です。
不定愁訴=自律神経失調症という考え方をしていないことが、私の基本概念となっています。
続きはまた次回以降とさせて頂きます。
自律神経失調症について その1
2019年10月22日 23:31更新
専門外来コラム
久しぶりに専門外来についてのコラムを書かせて頂きます。
自律神経失調症についての話をしていこうと思います。
それ以外の項目についても、不定期になりそうですが、ブログに書いていけたらと考えています。
2018年12月14日に出版となった拙書「最高のパフォーマンスを引き出す自律神経の整え方」から抜粋と一部手を加えての内容となっていく予定です。本の順番どおりではありません。
当院では、「頭痛外来」、「肩こり・首こり外来」、「自律神経失調症外来」、「気象病・天気病外来」、「寒暖差疲労外来」という特殊外来を開設しております。
自律神経失調症外来を受診される方で、私の説明を聞いて??と思われる方は多いです。
その理由は、私の自律神経失調症に対しての捉え方が、一般的とは異なっているからです。
通常でいえば、自律神経失調症というと精神的なストレスがメインであるという認識が強くあります。
自律神経
→ややこしい、理解しにくい、面倒くさい。これは、一般の方、医療関係者でも同じ場合が多い。
→動悸、めまい、全身倦怠感+慢性疲労、息苦しさ・呼吸苦、喉のつまり・違和感、不眠・睡眠の乱れ、腹部の不調などの様々な症状の原因が説明できない(原因が診察や検査でも確定できない)→これらの症状が1つではなく、複数ある。
→不定愁訴と診断される=自律神経失調症 という保険病名で説明が出来てしまう。
→悩んでいる方もそれで説明ができてしますので、納得してしまう。
→ストレス社会だから、精神的なストレスがメインだよね。
これが落としどころとなっていると考えています。
このような事が多々見られています。何故そう思うのかと、患者さんに話を聞くと、
①インターネットの情報で自律神経失調症に一致する
②医療機関で自律神経失調症と診断された
③家族や知人に自律神経失調症じゃないのか
と言われた。と話される方が多いです。
私自身の臨床経験では、精神的なストレス→自律神経失調症では、患者さんに納得のいく説明は出来ません。
46P~51Pからの引用です。
自律神経が乱れる原因は「精神的ストレス」だけではない
さて、「自律神経を整えよう」と思ったら、どのようにすればよいのでしょうか?
それを知るために、まず、「自律神経にはどんなことが影響するのか」ということを確認していきましょう。
自律神経に影響を与える主な要因は、ストレスです。
一般に、ストレスというと、「精神的な負荷」を意味すると認識されています。
しかし、1章でも述べたとおり、ストレスといっても精神的なものだけではありません。「身体的なストレス」、「環境的なストレス」も立派なストレスです。
医学・心理学においては、心と体にかかる外部からの刺激を「ストレッサー」と呼びます。そして、ストレッサーに適応しようとした結果、心身に生じるさまざまな反応を「ストレス反応」と呼びます。
ストレッサーには、次の4つがあります。
・物理的ストレッサー(暑さ・寒さ、騒音、混雑、悪臭など)
・化学的ストレッサー(酸素の欠乏・過剰、公害物質、薬物など)
・生物的ストレッサー(炎症、細菌・ウイルスの感染、睡眠不足など)
・心理・社会的ストレッサー(人間関係や社会生活上の問題など)
「ストレス」と聞くと、 「心理・社会的ストレッサー 」が真っ先に思い浮かぶ方が多いと思います。
しかし、実際には、暑さ・寒さなどの環境的要因によるストレスや、ウイルス感染や睡眠不足などの肉体的要因も含まれるわけです。
法律で定められている「ストレスチェック制度」からも、そのことがわかります。
これは、定期的に労働者のストレス状況について検査を行い、本人に結果を通知して自らのストレス状況に気づきを促し、個人のメンタル不調のリスクを軽減させるとともに、検査結果を集団的に分析し、職場環境の改善につなげることを主な目的としています。労働者が 50 名以上いる事業所において義務付けられているため、毎年受けている方も多いでしょう。
ストレスチェックというと、精神的な要因を連想されると思います。しかし、身体的な要因や、環境的な要因に当てはまるものも多いのです。
厚生労働省が提供するチェック項目「職業性ストレス簡易調査票」から、当てはまるものをいくつか抜粋します。
【STEP1仕事について】
→「そうだ、まあそうだ、ややちがう、ちがう」のいずれかで回答します。
・非常にたくさんの仕事をしなければならない
・時間内に仕事が処理しきれない
・一生懸命働かなければならない
・かなり注意を集中する必要がある
・からだを大変よく使う仕事だ
・私の職場の作業環境(騒音、照明、湿度、換気など)はよくない
など
【STEP2 最近1ヶ月の状態について】 →「ほとんどなかった、ときどきあった、しばしばあった、ほとんどいつもあった」
のいずれかで回答します。
・ひどく疲れた
・へとへとだ
・だるい
・めまいがする
・体のふしぶしが痛む
・頭が重かったり頭痛がする
・首筋や肩がこる
・腰が痛い
・目が疲れる
・動悸や息切れがする
・胃腸の具合が悪い
・食欲がない
・便秘や下痢をする
・よく眠れない
など
抜粋したのは、身体的要因や環境的要因と考えてよい部分です(もちろん、精神的ストレスを受けた結果身体に影響が出てきているという部分もあります)。
57 あるチェック項目のうち、 20 程度となります。全体の3分の1程度ですね。
このことからもうかがえるとおり、もっと物理的・化学的・生物的ストレッサー、つまり身体的なストレス・環境的なストレスの影響について考えるべきではないでしょうか。
精神的なストレスで自律神経が乱れることはよくあります。一方で、身体的・環 境的なストレスで自律神経が乱れることもよくあります。
しかし、「自律神経の乱れ」というと、「精神的ストレスのせい」という解釈に行き着いてしまうことが多いのが現状です。これでは、残念ながらよい結果に結びつく可能性は低いでしょう。
心・体・環境、トータルで考えてみてください。
続きは次回以降で。
低血圧の治療と対処法について。
2018年5月5日 16:50更新
専門外来コラム
低血圧の治療と対処法について。
まずは、低血圧であるという認識を持つこと。
次に、生活スタイルなどを見直すこと。
そして、薬物治療。
生活について
①立ち上がりに注意:急に立ち上がるとめまいを引き起こしやすいためです。2段階で立ち上がる、物につかまってゆっくり起きるをすすめています。
②睡眠をしっかりと:6時間くらいは睡眠を取るようにすすめています。
③適度な運動やストレッチ:ウォーキングやジョギング、ストレッチ、ラジオ体操など、簡単に行えること+継続できることが重要です。
④日光を15分/日程度あびる:これは、生体内のリズムを整えるためには大事なことです。
⑤体を冷やさない:特に女性は冷え性の方が多いので、暑い時でもカーディガンなどの羽織れるものを持ち歩くことが大事です。
⑥冷たい食べ物は少なめに:体内から冷やしてしまうことは、冷え性をさらに強めてしまいます。厳格に制限するというよりは気をつけるようにして下さい。低血圧のある方には要注意です。
⑦塩分を多めに取る:高血圧のある方には禁忌です。塩分を多めに取ることで、血圧は上がりやすいです。健康のためには、塩分は低めが基本とされていますが、低血圧の方が健康を維持するためには、血圧を上げることが重要なのです。20~30g/日が目安です。漬物や汁物を取ることが簡単な方法です。
⑧入浴する:40℃前後のお湯に首までしっかりと10分程度つかることをおすすめしています。しかし、低血圧の方は入浴で血圧が下がりやすいのでご注意を。
⑨深呼吸する:3秒吸って→3秒止める→6秒吐く→3秒止めるという方法をすすめています。リラックスできると感じた方はたまに行うようにして下さい。苦しい、ストレスに感じる方は行わないでください。
⑩ストレスを溜めない:現代社会ではこれが一番難しいのではないでしょうか。嫌なことを避けるよりは、楽しいことをする時間を増やすことが良いです。笑っている時間が多くなると理想的です。
楽しいことでも、パソコンやスマホの使用時間が長くなることはおすすめしません、その理由は、首肩のこりから、最終的に自律神経を乱してしまいます。結局は低血圧の方は、それがより強く出ることになってしまうからです。
⑪好きな音楽を聴く、歌う:好きなジャンルで構わないです。クラシック、ジャズ、邦楽、洋楽何でも良いでしょう。
次に、薬剤での治療についてです。
血圧を上げる薬。これは交感神経に作用します。
①メトリジン(商品名):一般名 ミドドリン
交感神経α受容体を刺激する薬で、主に末梢の静脈を収縮させる事で血圧を上げることになります。
当院で第一選択として使用している理由として、口腔内崩壊錠があるからです。起床時に、水なしで使用することが出来るのが利点です。
当院を受診される方は起き上がるのが困難なほど症状が強い方が多いため、水分なしで使用できる方が良いと判断しています。
②リズミック(商品名):一般名 アメジニウム
ノルアドレナリンが不活性化することを防止して、交感神経を刺激して、静脈の鬱血を改善する作用と心臓からの血液拍出量を増やす作用があります。
メトリジンと比較するとこちらの方が効果は強いです。
西洋薬でも他にも選択肢はありますが、この2つをメインで使用しています。
漢方薬:低血圧に使用するのではなく、随伴症状に使用しています。
③五零散: むくみ、めまい、頭痛、二日酔、下痢、悪心、嘔吐、の治療に使用されます。
④当帰芍薬散:冷え性、貧血、倦怠感、更年期障害、月経不順、頭痛などの治療に使用されます。冷え性+生理周期での頭痛がある方には、選択することが多い薬です。
⑤桂枝茯苓丸:月経不順、月経痛、更年期障害、冷え症、頭痛のある方に選択することが多い薬です。
⑥半夏白朮天麻湯:めまい、頭痛、肩こりがある方には、選択することが多い薬です。
⑦葛根湯:かぜ薬のイメージが強いと思いますが、肩こり、頭痛、血行の悪い方に効果が出やすいです。
などです。他にもたくさんありますが、当院で使用している主な漢方を載せています。ちなみに、保険適応内で症状が当てはまる場合に使用しています。
私の考え方としては、以下の2パターンで考えています。
五零散と半夏白朮天麻湯は、むくみに効果が出やすいです。
当帰芍薬散、桂枝茯苓丸、葛根湯は血流の停滞(肩こりや冷え性)などに効果が出やすいです。
ビタミン
⑧ビタミンB群:TCAサイクルという体内でエネルギー産生する過程でビタミンB群が必要となってきます。ビタミンBには様々な種類がありますが、その説明は今回は割愛させて頂きます。低血圧の方は、エネルギー産生が少ない方が多いので、ビタミンB群を取ることをすすめています。食事でも、サプリメントを使用するのも良いでしょう。低血圧では保険適応にはなりません。
⑨ビタミンE:ビタミンEが足りなくなると、血行が悪くなります。そのため、冷え性や肩こり、頭痛の原因となります。これらの症状を低血圧の方は併存している方が多いため、使用することで症状の改善が期待できます。直接血圧を上げるわけではないです。こちらも低血圧では保険適応にはなりません。
サプリメント
⑩コエンザイムQ10(出来れば還元型:体内への吸収が良いので)
コエンザイムQ10は、脂肪や糖からエネルギーを産生するときに働きます。細胞内にあるミトコンドリアがエネルギーを作るのですが、コエンザイムQ10が補酵素として働きます。
そのため、コエンザイムQ10が多いと効率よくエネルギーを産生できます。全身のエネルギー産生への効果を期待できますが、特に心筋での効果は高いと言われています。
低血圧の患者さんに使用すると、心拍出量が増加します。
保険適応でないため、市販のコエンザイムQ10をすすめています。ドラッグストアのサプリメントのコーナーに大体数種類は置いています。
⑪抗不安薬、抗うつ薬
効果はあるのですが、副作用として、血圧低下や倦怠感などがあります。長期間の使用で依存も出やすい事が難点です。
当院では、必要に応じて、少量から使用しています。
薬剤の細かい説明はあえてしません。何故かというと、当院を受診される方は、いくつかの抗不安薬や抗うつ薬を使用されている場合が多いためです。低血圧が原因の場合に、先に選択すべき薬ではありません。
低血圧について
2018年4月10日 23:46更新
専門外来コラム
低血圧についてです。
低血圧とは、収縮期血圧(最大血圧)100(mmHg)以下、拡張期血圧(最低血圧)60(mmHg)以下の事をいいます。
高血圧と違い、症状がなければ治療をしなくても良いというのが一般的な考えです。そのため低血圧はあまり臨床的には注目はされていません。当院の専門外来を受診される方には、坐位や立位の血圧測定にて、低血圧を認めることが多くみられます。
低血圧に伴う症状には、以下のものがあります。
① 立ちくらみ、めまい。ひどくなると失神する。
② 立っていると気持ちが悪くなる。動悸や息切れが起こる。
③ 入浴後に体調不良になりやすい。
④ 朝起きるのが苦手である。
⑤ 全身倦怠感がある。
⑥ 顔色が悪い、青白い。貧血がある。
⑦ 食欲不振や胃もたれ、腹痛が起こりやすい。食後に体調が悪くなりやすい。
⑧ 頭痛、首こり、肩こりがある。臥位の場合は出にくい。
⑨ 精神的ストレスで体調不良になりやすい。
⑩ 気象変化に弱い。乗り物酔いをしやすい。
他にもありますが、分かりやすく10項目にしています。
当院で行なっている専門外来での症状に一致することが多いです。首肩こり、貧血、自律神経失調症などと相互に関係していると考えています。そのため、当院では低血圧を疑う方には自宅での血圧測定をおすすめしています。特に起床時の血圧が重要です。
緊張しやすい方は、診察室では緊張して血圧も上がってしまうので、低血圧は隠れやすくなってしまいます。
低血圧には、急性低血圧と慢性低血圧があります。
急性低血圧には、アレルギー(アナフィラキシーショックなどで急激に血圧が低下します)、ショック症候群(外傷による血管外への出血、心筋梗塞などの心機能低下など)、アルコール(空腹でアルコールを飲んで急速に吸収されて血管拡張による血圧低下)によるものなどがあります。
急性低血圧の方は、それぞれの原因に対しての適切な治療が必要となります。
慢性低血圧には、体質性低血圧と症状を伴う、起立性低血圧、本態性低気圧、症候性低気圧などがあります。
起立性調節障害は厳密には起立性低血圧とは違いますが、よく似ています。当院の患者さんでは、起立性調節障害と診断され治療されている方は、比較的が多いです。以前書いた起立性調節障害のブログを参照されてください。
体質性低血圧:常に低血圧ですが、症状が全くないため問題ありません。
本態性低血圧:明らかな原因がなく慢性的に低血圧な場合です。症状がない場合は、体質性低血圧となっていると考えて良いでしょう。
血圧が低いのを自覚していたり、指摘されるため、当院に来る際にはすでに診断されている方が多いです。
症候性低血圧:貧血、糖尿病や悪性腫瘍、甲状腺機能低下症、パーキンソン病などの神経難病、その他様々な疾患が原因となっています。
起立性低血圧:臥位では収縮期血圧が100mmHg以上あるが、立位になると80mmHg以下にも下降する状態です。
収縮期血圧が21mmHg以上下がる場合となります。
起立性低血圧が起る理由には、自律神経が関係しています。
自律神経は、交感神経と副交感神経に分かれています。交感神経は血圧を上昇させ、副交感神経は血圧を低下させます。起立直後に下がる直後型、時間が経って起きる遅延型の2つがあります。
起立性低血圧が起るメカニズムについて説明をします。血圧維持に関しては以下のシステムとなっています。
① 立ち上がると頭部への血流が減る。頭部へ行く血管は総頚動脈と椎骨動脈があります。特に総頚動脈の血流が多いです。
② 血流を減ったことを、頚動脈洞で感知します。
③ その信号が、自律神経を通じて、脳幹にある血圧中枢に伝わります。
④ 交感神経が優位になることで、心拍数の増加と末梢の血管を収縮させて、脳への血流を保持します。
この一連の流れがスムーズに行けば、起立性低血圧は起きません。
起立性低血圧は、寝ていてから起きるとき、特に早朝時に起きやすいです。これは、寝ているときは副交感神経が優位なためです。起き始めには、まだ活動モードの交感神経にうまくスイッチが入っていないと考えるとわかりやすいでしょう。
高齢の方では、動脈硬化が強い事が原因となりやすく、直後型の低血圧となることが多いです。
思春期や成長期の方では、成長発達段階(自律神経もまだ発達途中)のため起きやすくなります。起き上がることができない場合と遅延型が起きることが多いです。
思春期や成長期では、起立性調節障害と診断されることが多く、治療としては同じような薬を使用します。
骨格が急速に大きく来ることに、自律神経系が対応出来なくなっている場合や姿勢のゆがみ、首肩こりなどの自律神経の乱れやすい状態で起きやすくなります。朝気圧が下がっていると、低血圧のため、体が動かないという症状を持っている方は当院では多いです。
朝礼中に気持ち悪くなったり、めまいがしたりなどの体調不良、酷くなると意識をうしなったりする場合があります。立ち仕事を長時間されていて出る方もいます。
遅延型では、自律神経が乱れている方が起きやすいです。自律神経が乱れやすい骨格の状態の方が起きやすいと臨床では感じています。
貧血と間違われることもありますし、合併していることもあります。
様々な要因が低血圧と関係しますので、総合的な判断が必要となります。
治療や対処法に関しては、次回に書いていこうと思っています。
機能性胃腸症と姿勢の関連性について
2018年2月15日 20:50更新
専門外来コラム
機能性胃腸症(機能性ディスペプシア:FD functional dyspepsia)についてです。
FDと姿勢が関係していると考えたため、記述することにしました。
当院での内科は総合内科、神経内科なので科が違うのではと思われるかもしれません。
その通りで、当院では上部消化管検査や下部消化管検査は受けることは出来ません。
専門外来を受診される方で、胃の症状を訴える方は多いです。特に、慢性的な吐き気、心窩部痛、食欲はあるがお腹がすぐに一杯になるなどです。
当院で頭痛、肩こり首こり外来、自律神経失調症外来、気象病外来において、専用のチェックリストを作っています。その中で、胃部症状のチェックがあります。
□吐き気 □胃痛 □胃酸上昇 □逆流性食道炎 □下痢 □便秘
となっています。ここにチェックをされている方は、腹部症状があり、特に胃周辺にある方は、FDと診断され、投薬治療を受けている方は、かなりおいでになります。
まずは、FDがどういう疾患なのかを説明されて頂きます。
概念:FDとは、上腹部の痛みや不快感や腹部膨満感、吐き気、むかつきなどの上腹部症状を慢性的に訴えているが、明らかな器質的疾患が認められないことをいいます。
診断基準:ROMEⅢの診断基準 2006年より引用
1. 以下の症状のうち1つ以上の症状が6ヶ月以上前から起り、最近3ヶ月は症状が続いている。
A食後のもたれ、B早期膨満感、C心窩部痛、D心窩部灼熱感
2.かつ症状の原因となりそうな器質的疾患(上部内視鏡検査を含む)が確認されないもの
上記のうち、AまたはBが主症状であるものを食後愁訴症候群
PDS:postprandial distress syndrome
上記のうち、CまたはDが主症状であるものを心窩部痛症候群
EPS:epigastric pain syndrome
をもとに、2014年に日本消化器学会が作成した
機能性消化管疾患診療ガイドライン2014-機能性ディスペプシア(FD)
というガイドラインがベースとなっています。
原因:胃適応性弛緩性障害、胃排出障害、ヘリコバクター・ピロリ感染、内臓知覚過敏、アルコール、喫煙、ストレスや不安などの社会的因子、遺伝的要因などがあり、それが複雑に影響し合っていると考えられております。
治療:消化管運動機能改善薬、胃酸を抑制する薬を使用したり、胃の粘膜を保護する薬を使用したりします。ヘリコバクター・ピロリ感染がある場合には、除菌療法が必要とされています。漢方薬も効果を示します。それで効果が無い場合には、抗うつ薬や抗不安薬を使用することがあります。
ここからは私が臨床的に経験したことを説明させて頂きます。
論理的な裏付けがないと言われそうですが。
消化器専門医にて、FDと診断され治療を受けているがあまり効果が出ていない方に共通している部分。
1:姿勢が悪い、座っているときに猫背か、首が結構前に出ている
2:肩や首、背中がこっている(自覚症状があるなしに)
3:鎖骨の下を押すと痛い
4:腹部側面の肋骨を押すと痛い
→これは骨格的なゆがみがあるということなのですが。
骨格的なゆがみが出る理由
A:首が前に出る
B:PC作業やスマホ使用で手が回内する→肘も回内する→肩も回内する
C:肩の位置に左右差がある
D:骨盤の位置で前傾、後傾、左右差などがある
他にもありますが、特にA、BがFDの症状に関係しています。
人間の体幹は、胸部は心臓と肺があるため、胸骨、肋骨、鎖骨、背骨などでガードされています。しかし、腹部は背骨しかありません。
首が前に出て、肩が内巻きになると、胸郭が腹部を圧迫します。上から押されているわけですから、消化管内を調べても原因がはっきりしない。
当院を受診される方でFDの方に対して、姿勢の変化で胃部症状がどうかをチェックしています。姿勢を理想的(骨盤が立った状態、肩が開いた状態、首があまり前に出すぎていない状態)にしてみると、胃の不快感が改善することがとても多いです。
そんな簡単な事で治るはずがないでしょうと思われると思いますが、実際にその場ですぐに実感されている患者さんも多いです。
自分でFDと思われる方は、試しに以下の方法を行なってみて下さい。
① 椅子に座る
② 膝をそろえる。
③ 足首の角度、膝の角度、骨盤の角度が90°のイメージで座る
④ 胸を少し開く
⑤ 肩の上に耳を乗せるイメージで軽く顎を引く(この時に反り腰にならないように注意:腰を痛める可能性がある)
⑥ 視線をまっすぐに
この状態で、上腹部を軽く押してみて下さい。いつもの症状が改善した場合は、姿勢を正しくすることで症状が改善できると思って良いでしょう。
上記方法で改善した場合は、当院では数回の治療で良くなっています。自分で骨格を正しくすることが出来れば、それだけでもかなり変わってきます。
体幹や首や肩のストレッチや、ヨガ、負荷の少ない全身運動、PCやスマホを連続で使用しない、椅子の座り方を変えるなどのちょっとしたことで変わってきます。
カフェインを多く取られる方(5~6杯以上)は、FDだけでなく、慢性的な頭痛や肩こりに悩まされている方が多いです(特に男性に多い傾向があります)。
運動機能性外来について
2017年12月30日 11:31更新
専門外来コラム
運動機能性外来についての紹介をさせて頂きます。
当院では月1回、第4火曜日か第5火曜日の18:00~20:00の間、一人30分間の完全予約制で特殊外来を行っております。
運動機能性についての説明をします。
人体は頭部、頚椎、胸椎、腰椎、骨盤、四肢の骨格があります。
それに筋肉や筋膜、靭帯などが付着します。これらは、関節を中心として体の動きを出します。そして、皮膚があります。簡単に説明するために、内臓や血管、リンパなどの話しは今回は省いておきます。
骨格が正常の位置に無いことで、姿勢のずれが生じます。理想の骨格は左右前後のバランスが均等であることが理想です。実際には理想の骨格のバランスを得たままで生活することは困難です。利き腕や、利き足、咬み合せの左右差、PC作業の右マウス使用、スマホの持ち方など様々な事で左右差が出ます。左右差が出るのは当然なのですが、バランスがずれすぎたりすると、筋肉疲労や筋膜のこり、骨のゆがみや変形を引き起こします。
当院を開院してから、首こり肩こり外来、頭痛外来で治療を行いました。自律神経失調症で悩んでいる方が多く、自律神経失調症外来を始めました。自律神経が乱れている方は、気象の変動による体調不良を訴えることが多かったことから、気象病・天気病外来を始めました。気象病の治療で改善している方で、エアコンの影響によりまた体調不良になることが多かったことから、冷房病・エアコン病外来を始めました。
これらの専門外来の中で共通していることは、姿勢、骨格の歪み、筋肉のこり、左右差などが関係しています。
その例としては、片頭痛が右に起きている方は、右側に首が傾いている事や上部頚椎の異常が右で見つかる事、三叉領域の痛みが右に多い事などです。
右膝が痛い方も、姿勢が右に傾いていたり、骨盤の動きが右で悪かったり、足裏に差があったりなどです。
運動機能性を改善することが根本的な治療となることを実感しています。
しかし、当院の保険診療内での治療では、頚椎のずれや、骨盤のずれなどを治すことはなかなか難しい所がありました。鍼灸、整体、ヨガ、マッサージなど様々な治療家の方々と治療を行ってきました。
私は脊椎や骨格の歪みが自律神経の乱れも引き起こし、一件関係なさそうな様々な症状を引き起こすという考えに至っています。その考え方と最も合致するものがカイロプラクティックでした。
骨をボキボキする怖い感じの治療というイメージをお持ちの方が多いでしょう。
骨格の歪みが強い方を、カイロプラクティック治療の専門家に紹介をしていると、良好な結果を得ることが増えました。当院での治療が必要なくなる方も多くなりました。
片頭痛で悩んでいる方が長期間来なくて、久しぶりに来院されると、頭痛回数が減ったから来なかったんですよ言われました。
カイロプラクティックでの治療結果が出ていた方のレントゲンを取ると、当初にあった姿勢の左右差やストレートネックの改善を認めていました。
その事から、診療時間内ではカイロプラクティックでの治療は出来ないため、月1回運動機能性外来を始めました。治療後に症状の改善(首の痛みが軽減、肩が上がるようになった、腰痛が軽減したなど)を認めると、レントゲン所見も良い方に変化していることが多く見られます。
来年もこの運動機能性外来で得た治療ノウハウを、保険診療内でも反映できるようにしたいと思っております。
下にはカイロプラクティックがどういうものかを簡単にまとめています。
一般社団法人 日本カイロプラクターズ協会 から許可を受けて添付しています。
カイロプラクティック(Chiropractic) 【業界の定義】
筋骨格系の障害とそれが及ぼす健康全般への影響を診断、治療、予防する専門職であり、関節アジャストメントもしくは脊椎マニピュレーション(アジャストメント)を含む徒手治療を特徴とし、特にサブラクセーション(神経系の働きを妨げ生理学的変化を起こす因子)に注目する。
(世界保健機関, 2005年)
カイロプラクティック(Chiropractic) 【一般の定義】
カイロプラクティックは身体の構造(特に脊椎)と機能に注目した専門医療です。カイロプラクティックの施術法は、施術者によって様々ですが、主に脊椎やその他の身体部位を調整(矯正)することにより、ゆがみの矯正、痛みの軽減、機能改善、身体の自然治癒力を高めることを目的としています。
(厚生労働省, 2014年)
分かりやすく言えば、骨格のゆがみ、特に背骨の機能異常を手技によって調整することで神経の働きを回復するヘルスケア(保健医療)です。すなわち人間の体を主にコントロールするのは脳につながる神経系であり、その働きがよくなれば自然に人は症状の改善とともに健康になるという訳です。
カイロプラクティックのアイデンティティー
○ ヘルスケア・システムの中における脊椎ヘルスケア(保健医療)の専門家。 ○ 神経筋骨格系の機能、健康全般そして生活の質を向上させる能力を有する。 ○ 最新の研究および臨床経験に基づき、特に脊椎と神経系の関係を重視しながら検査、診断、治療に専門的なアプローチを行う。 ○ 手技療法、体操療法、患者教育などを含みながら、特に脊椎アジャストメントを行う教育を受けた専門家。
(世界カイロプラクティック連合, 2005年)
カイロプラクティックの治療法
カイロプラクティックでは、まず病歴を取り、姿勢分析など各種検査を行います。そして身体の歪みを総合的に判断して治療の順序を組み立て、病状や個人差に応じた手技のテクニックを用います。 カイロプラクティックは薬物で病状を押さえるのとは違い、神経の働きを良くし自分の体内にある薬を活用する自然療法です。その為、背骨など骨格の調整だけでなく、姿勢体操、栄養、睡眠などの生活指導も行います。またカイロプラクティックは予防医学として健康管理にも利用されております。
適応症
腰痛、頭痛、むち打ち、肩こり、股関節や膝の痛みなど運動器疾患系にすぐれた効果を発揮します。その他、疲労回復、姿勢改善、自律神経失調、など、また自律神経を介して内臓の機能改善、ストレスの緩和などにも有効であり、高齢者へのケアや生活習慣病、慢性病などの効果も注目されています。風邪予防や健康増進のため、健康管理としても利用されています。
禁忌
刺激を避けなければならない病気(癌、出血しやすい病気、高熱の出る病気、伝染病など)
気象病の記事が掲載されました。
2017年12月21日 19:02更新
専門外来コラム
薬物乱用頭痛(MOH:Medication Overuse Headache)について
2017年12月14日 21:53更新
専門外来コラム
頭痛外来を受診される方の中には、
月に半分以上、頭痛のために鎮痛薬飲んでしまっている方が多く見られ、その中には薬物乱用頭痛となっている方が多いです。
月に10日以上鎮痛薬を飲んでいる、出そうだから早めに飲む、は要注意です。
頭痛が起こる。→鎮痛薬を飲むとおさまる→また頭痛が起こる→鎮痛薬を飲むとおさまる
どんどん効果時間が短くなりさらに飲む回数が増えるという悪循環に陥ります。
このようなサイクルになってしまい、根本原因の軽減が出来ていないため、鎮痛薬を飲み続けることになってしまいます。そのうち同じ薬では効かなくなり、その他の薬、多剤併用になってしまうことも多く見られます。
さらには、頭痛が起きそうな感じがすると鎮痛薬を飲んでしまう方が多いです(この出そうだから鎮痛薬を飲むという行為は乱用を引き起こす可能性が高いです)。
1回MOHになってしまうと、なかなか抜け出せなくなります。
緊張型頭痛、片頭痛、緊張型頭痛+片頭痛の混合型が改善しないため、鎮痛薬の服用が多くなってしまいます。
MOHは、緊張型頭痛、片頭痛の次に多いと言われております。実際に当院でもその割合となっています。男女比は女性に起こりやすいです。中学生以降では見られます。ストレスの多い方や、PCやスマホの使用時間の多い方にも多いです。
原因となる薬剤は、①市販の鎮痛薬(カフェインを含んだり、数種類の鎮痛成分が入っているのはよりなりやすいです)、 ②NSAIDs等の鎮痛薬、③トリプタン製剤、 ④エルゴタミン製剤(使用頻度が減っているため、単独で原因となっていることは少なくなっています)などがあります。
上記①~④を併用している方も多く見られます。
トリプタン製剤の処方されている方は、他の製剤より早い期間でなってしまうことが多いとされています。
当院では、多剤を併用されている方により多くのMOHが見られています。
緊張型頭痛+片頭痛の混合型の方は、よりMOHの程度が強くなっています。
以下に示したのが、診断基準です。国際頭痛分類第3版beta版(ICHD-3β)からの引用です。
薬剤の使用過多による頭痛(薬物乱用頭痛)(MOH:Medication Overuse Headache)の診断基準
A:以前から頭痛疾患をもつ患者において、頭痛は 1ヵ月に15日以上存在する
B:1種類以上の急性期または対症的頭痛治療薬を 3ヵ月を超えて定期的に乱用している
C:ほかに最適な ICHD-3 の診断がない
エルゴタミン乱用頭痛
3ヵ月を超えて、1ヵ月に10日以上、定期的にエルゴタミンを摂取している
トリプタン乱用頭痛
3ヵ月を超えて、1ヵ月に10日以上、定期的に 1つ以上のトリプタンを摂取している(剤形は問わない)
単純鎮痛薬乱用頭痛
3ヵ月を超えて、1ヵ月に15日以上、単一の鎮痛薬を摂取している
オピオイド乱用頭痛
3ヵ月を超えて、1ヵ月に10日以上、定期的に 1つ以上のオピオイドを摂取している
複合鎮痛薬乱用頭痛
3ヵ月を超えて、1ヵ月に10日以上、定期的に 1つ以上の複合鎮痛薬を摂取している
治療の流れは以下となります。
- 原因薬物を中止する:多剤使用している場合は、より飲んでいる回数が多い薬から中止していきます。
- 薬物中止後に起こる頭痛(反跳頭痛)に対する治療:ここを乗り切れないと減っていきません。2週間くらいの期間続くことをしっかりと説明しておくことが重要です。鎮痛薬をゼロにしなくても良いから、ギリギリまで飲まないようにしましょうと伝えています。ゼロと言われると、必要以上のプレッシャーとなってしまいます。
- 予防薬の投与:緊張型頭痛には、筋弛緩薬や漢方薬など。片頭痛には、抗てんかん薬、βブロッカー、漢方薬など。
- 頭痛ダイアリーの使用:頭痛が出た日数や時間帯、薬物使用日数を付けることによって、患者さん自身が自分の状態を把握できるようになります。出来れば、天気も書いてもらいます。
- 飲んで良い鎮痛薬の種類や回数:それとしっかりと伝えること、そして鎮痛薬を10回/月以内に抑えること
- ストレッチやマッサージ、ストレッチなどの運動療法:自分に合う方法なら何でも構わないです。日々の心身の疲れやストレスをリセットするためには、とても重要です。
- 気象病がベースにある場合は、そちらの治療も並行して行います。
気象病の治療を行うようになってからは、MOHからの離脱成功率が上がってきております。
貧血について
2017年12月2日 16:33更新
専門外来コラム
貧血とは、体内に鉄が欠乏している状態です。
一般的には、血液中のHb(ヘモグロビン)濃度が低下している事を指しています。
貧血では、肩こり、頭痛、めまい、倦怠感、動悸、息切れ、冷え、寒暖差疲労など様々な症状が出現します。
当院の専門外来である頭痛・肩こり外来、自律神経失調症外来、気象病外来を受診される方にも、貧血や隠れ貧血はよく見られます。
細胞には酸素が必要です。呼吸によって肺に取り込まれた酸素は、赤血球内のヘモグロビンと結合して、四肢末端まで運ばれます。
そのため、体内に鉄分が不足すると様々な悪影響を及ぼします。
成人の鉄総量は3-5gです。その割合に関しては、下記で述べます。
1日に1mgが体外へ出ていきます。女性では生理出血で20-30mgを失うとされています。
貧血の原因は、様々ですが、最も多いのが鉄欠乏性貧血です。
女性に多い理由は、生理周期で出血を伴うことが一番の理由です。
その他の理由としては、腎臓の機能障害に伴う腎性貧血、慢性炎症(関節リウマチなど)に伴う貧血などが挙げられます。
ここでは鉄欠乏性貧血について話していきます。
健康診断などの採血では、ヘモグロビン(Hb)、ヘマトクリット(Ht)、MCV(平均赤血球容積)、MCH(平均赤血球血色素量)、MCHC(平均赤血球ヘモグロビン量)、Fe(血清鉄)などです。
フェリチン、Fe(血清鉄)、TIBC、UIBCという数値は、健康診断ではあまり測定されません。
人間ドックでは測定されることもあります。
下記が鉄に関する基準値や参考値となります。
|
検査項目 |
基準値 |
|
赤血球数 |
女性 380万~480万 個/μl 男性 410万~550万 個/μl |
|
ヘモグロビン |
女性 12-16 g/dl 男性 14-18 g/dl |
|
Ht |
女性 36-45 % 男性 40-50 % |
|
MCV |
81-100 fl |
|
MCH |
27-32 pg |
|
MCHC |
31-36 % |
|
Fe |
女性 50-170 μg/dl 男性 60-210 μg/dl |
|
TIBC |
女性 260-420 μg/dl 男性 250-385 μg/dl |
|
UIBC |
女性 130-380 ng/ml 男性 110-330 ng/ml |
|
フェリチン |
女性 5-157 ng/ml 男性 20-280 ng/ml |
用語の説明:簡単な説明なので足りない部分はあると思います。
ヘモグロビン:赤血球の中にあり、ヘムとグロビンという物質が結合しています。ヘムは酸素と結びつく性質があります。
ヘマトクリット:血液中に占めている血球体積のわりありです。
MCV(平均赤血球容積):これは赤血球の大きさです。
MCH(平均赤血球ヘモグロビン値):赤血球1個あたりに含まれるヘモグロビン量の平均値。
MCHC(平均赤血球色素濃度):一定容積の赤血球に含まれるヘモグロビン量の平均値。
TIBC(総鉄結合能):血液中のトランスフェリンが鉄と結合できる総鉄量を示しています。
UIBC(不飽和鉄結合能):血液中の鉄と結合していないトランスフェリンを示しています。
トランスフェリン:トランスフェリンは肝臓で生成されるタンパク質です。血液中の鉄と結合する働きがあります。
フェリチン:内部に鉄分を貯蔵できるタンパク質です。鉄を細胞内に貯蔵して、トランスフェリンと鉄の交換を行なって、血液中の鉄を維持しています。
鉄の役割分類:
体内の鉄には、機能性鉄、貯蔵鉄、運搬鉄の3つの分類となります。
①機能性鉄は、ヘモグロビン(他にもありますがここでは省略します)が大半を占めております。体内の鉄量でも60~70%です。そのほかに、ミオグロビンやチトクロームがあります。
②運搬鉄には、トランスフェリンがあります。体内の鉄量の0.2~0.3%位です。
③貯蔵鉄は、フェリチンがあります。これは、体内の鉄量の25%前後です。肝臓や脾臓、骨髄や腸管に貯蔵されています。
割合から考えると、ヘモグロビンとフェリチンが重要になります。
体内の鉄分は、2/3がヘモグロビンの中に存在しています。残り1/3の中でも重要なのが、フェリチンとなります。
ヘモグロビン量が正常範囲内だと貧血ではないと思いがちですがそうではありません。
体内のストック分のフェリチンが少なくなると、隠れ貧血となってしまいます。
隠れ貧血でも、貧血の症状は出るのです。
先ほどから色んな数値が出てきていますが、当院で目安としているのは、Hb、Fe、フェリチンを目安にして以下の判断をしています。
当院では、
正常
軽めの隠れ貧血
重めの隠れ貧血
鉄欠乏性貧血
の4つで判断しています。
女性の場合で表にしてみます。おおよそ目安になります。
|
Hb g/dl |
Fe μg/dl |
フェリチン ng/ml |
|
|
正常 |
14以上 |
110以上 |
100以上 |
|
軽めの隠れ貧血 |
13~14未満 |
50-100 |
50~80 |
|
重めの隠れ貧血 |
12~13未満 |
50-100 |
20~50未満 |
|
鉄欠乏性貧血 |
11以下 |
50以下 |
20以下 |
正常、貧血、隠れ貧血で判断をして、臨床的な症状と合致するかが重要となってきます。
貧血、隠れ貧血で症状が出ている方は、Hbが13g/dl以上、フェリチンが50 ng/mlを超えるまでは、貧血の治療を勧めています。
上記の表にあるように、全て正常なのが理想ではありますが、そうでなくても症状の改善は見られます。
貧血や隠れ貧血には注意をされて下さい。
※鉄剤等の投薬には診察により保険適用外となる場合もあります。
寒暖差アレルギーについて
2017年11月13日 07:53更新
専門外来コラム
今日の朝も寒いですね。
11/13月曜は、午前中はまだ晴れていますが、気圧は午前から少し下がってきそうです。雨も降りそうな予想になっています。明日まで、雨は降る可能性が高いようです。
さらに気をつけないと行けないのは、雨が降った後寒気が南下してくるようです。
気温がより下がってくる可能性があり、ご注意されて下さい。
寒暖差アレルギーについて簡単にまとめました。
1:寒暖差アレルギーとは
温度差が大きいときに引き起こされる症状です。アレルギーとなっていますが、実際にはアレルギー反応ではなく、自律神経の乱れに伴う反応です。正式病名としては血管運動性鼻炎になります。
2:症状
起きやすい症状は、鼻水、くしゃみ、鼻づまり、咳。その他、不眠、イライラ、倦怠感、食欲低下、皮膚の痒みや湿疹などです。
自律神経は、周りの環境に対して体を自動調整します。寒い場所では、血管が収縮します。暖かい場所では、血管が拡張します。
自律神経が、適切な対応が出来るのは大体7℃以内と言われています。
7℃以上の気温差で鼻粘膜の血管が拡張して鼻粘膜が浮腫して、アレルギー様の症状が出ます。春や秋などの寒暖差が強くなるときに出やすい。しかし、最近では夏(室内がクーラーで冷えている)や冬(室内で暖房が効いている)の室内外の温度差が強い場所でも起きやすくなります。
3:感染症、アレルギー性鼻炎との違い
・感染症は、咽頭痛や発熱、粘稠性の鼻水、咳嗽などを伴います。
・アレルギー性鼻炎は、スギやダニ、ハウスダスト等の原因物質が鼻粘膜に付着することで発症します。眼の痒み、充血、涙などの眼の症状を伴うことが多いです。
寒暖差アレルギーは、検査をしても特に以上は見つかりません。眼の症状も出ることは少ないです。こちらは眼の症状は
4:対策
- 洋服をうまく調整して、寒暖差を減らす。
- マスクを使用して、寒暖差を減らす。冷たい空気が鼻・喉に直接来ないようにするため。
- 簡単にできるストレッチやマッサージ、ツボ押しなどを行う。
- 生活リズムを乱さないようにする。
- 夜寝るときに、首が冷えるので、首回りの防寒対策を行う。
- 40℃前後のお湯で体を暖める。
- 精神的なストレスを貯めないようにする。
5:投薬治療について
・内服薬:抗アレルギー薬の内服。アレルギー性鼻炎の時に出る飲み薬です。種類は、色々ありますが、副作用としては、眠気やだるさが出現することが多いです。
・点鼻薬:これには、大きく分けて2種類あります。血管収縮作用のあるものと、ステロイドです。血管収縮作用のあるものは、即効性がありますが、用法用量を守り、長期間使用しないようにしましょう。使用過多による、鼻粘膜が肥厚し、鼻粘膜の血管が広がってしまう、点鼻薬性鼻炎となってしまうことがあります。その際には、耳鼻咽喉科さんへの受診が必要となります。
自律神経失調症の疑い、気象病の方は、寒暖差アレルギーの症状の方は多いです。これは、自律神経が乱れがちなだと、寒暖差の影響を受けやすくなってしまうからです。
Blogメニュー
▶Blogトップ