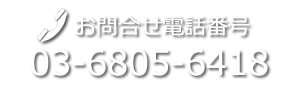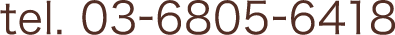「自律神経 これ1冊ですべて整える」が発売されます
2025年10月29日 07:53更新
専門外来コラム
10月コラム
「自律神経 これ1冊ですべて整える」東洋経済社 から発売されます。
「朝、何となくだるい」、「ベッドから起きるのがつらい」、「体が動かない」、「頭痛が治療をしても改善しない」、「めまいが改善しない」、「胃の不調が改善しない」など受診される方からお聞きすることが多いです。
頭痛は脳神経外科か脳神経内科で頭部MRIや診察で目立った異常はないとのこと。
めまいは耳鼻科で聴力検査やめまい検査で目立った異常はないとのこと。
動悸は循環器内科で心電図、レントゲン、心エコー、ホルター心電図、採血で目立った異常はないとのこと。更年期障害を疑い、婦人科で診察や検査を受けても、特には問題なしとのこと。
胃の不調があり、消化器内科で腹部エコー検査や、胃カメラを受けたが、特には問題ないとのこと。
原因がはっきりしないのはつらいですよね。
患者さんはつらい症状なので、生活習慣を変える、睡眠時間を確保する、食事をしっかりとる、ストレスをためない、運動をする、服薬をしっかり続けるなど様々な方法で対策をしています。
しかし、改善せずに悩まれている方で、当院の「頭痛外来」「首肩こり外来」「自律神経失調症外来」「気象病・天気病外来」「寒暖差疲労外来」を受診される場合が多いです。
この専門外来の中で、単独の外来を受診される場合以外に、頭痛外来と気象病外来、自律神経失調症外来と気象病外来というように、2つ以上を希望される方が結構おられます。
そのような場合に、診察をする際に大事にしていることがいくつかあります。
- まずは、1番目、2番目、3番目につらい症状を聞いています。いつからですか?
- 専門的な問診表+で必要と思われる項目を質問します。
- 診察をしていきます。一般的な内科的診察です。そして、神経内科専門医としての診察を行います。
- 専門的(当院での専門外来的)な診察を行います。
これらを判断して、どのような治療が適しているのかを決定しています。
そして、該当する患者さんの場合には、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲが関係しているのかを評価するようにしています。
Ⅰ:自律神経
どんな状態なのか(頭痛、首肩こり、めまい、動悸、だるい、倦怠感、立ちくらみ、午前中調子が悪い、寝付けない、長時間眠れない、気分が落ち込む、気分がアップダウンする、イライラする)を、話を聞くことが大事です。
「自律神経失調症じゃないかと思って」、「自律神経が原因だと思う」と話される方も多いです。
→ただ私からは、なるべく自律神経の話はしないようにしています。
自律神経が原因とされる場合は、心身の不調の割合を把握することが重要だからです。
「不調の割合」というキーワードを使用することが多いです。
- 心の不調が大きいのか、②身の部分が大きいのか、③心身が混在している。
この3つをなんとなく把握しようとしています。
Ⅱ:骨格(姿勢)
そして、診察開始に行うようにしているのが、姿勢、歩き方、座り方、頭の位置などをチェックします。このチェックで、頭痛の左右差、首肩こりの左右差があるのか、腰痛の左右差が把握しやすくなります。だるい、全身倦怠感を訴える場合にも、診断のポイントになる場合があります。
Ⅲ:気象
天気に影響を受けるのか?を問診でチェックするようにしています。
- 天候が悪い時に体調が悪い
- 雨が降る前や天候が悪化する前に、何となく天気の予測ができる
の2つの質問です。気圧、気温、湿度です。
このⅠ・Ⅱ・Ⅲのどちらが該当するのか。そして、3つの割合を比較するようにしています。
当院の専門外来は、頭痛外来→首肩こり外来(Ⅱに該当)→自律神経失調症外来(Ⅰに該当)→気象病外来・天気病外来(Ⅲに該当)→寒暖差疲労外来(Ⅲに該当)という順番になっています。
脳神経内科専門であったことから、頭痛を診察することが多く、頭痛(緊張型頭痛、片頭痛)には首肩こりが関係していました。
2013年の開業当時から、頭痛外来と首肩こり外来は、専門外来として立ち上げていました。
そして、自律神経失調症といわれる症状には、首肩こりが関係しているというホームページの内容をみて、受診される方が多くなりました。自律神経失調症で臨床的に説明できる方にも、首肩こり外来での同じような診断方法と治療(セルフケア、生活習慣、投薬)で
結果が出ました。
自律神経失調症を、心身の症状に当てはめていくことが重要であると実感して、自律神経失調症外来を立ち上げることになりました。私自身が、自律神経失調症を、検査をしても原因がわからない不定愁訴と捉えていた時期があっただけに、パズルが解けるような感触を得ていました。
しかし、頭痛やめまいを訴える方には、曇りや雨、台風、ゲリラ豪雨などで、症状が悪化する方が多かったです。
天気関係だよね、調子が悪くなるのは、当たり前だよねと考えていました(ただ診察をしていても自分自身で納得できていない部分がありました)。
天気の不調でも、特に気圧の変化で不調になる場合が多くみられていました。
開業から3年が経過して、不調の原因に天気が関係していることが多いという臨床経験が積み重なっていきました。
専門外来の必要性を強く感じて、
2016年9月に気象病・天気病外来を専門外来として立ち上げることになりました。
2017年5.6.7月の梅雨前後の時期には気象病(気圧差)の治療でそれなりの結果が出るようになりました。
しかし、夏場にエアコンで冷えて不調、外が暑くて不調の方が見られるようになりました。温度差による不調が原因でした。
2017年7月頃に、「冷房病・クーラー病外来」を立ち上げました。クーラーを使う夏場の不調が目立っていました。しかし、春(寒い時から暖かくなる時)と秋(暖かい時から寒くなる時)にも同様の症状がみられていました。温度差による体調不良が年間で起きていることが理解出来ました。
そして、2018年7月頃に「寒暖差疲労外来」へと名前を変えることになりました。
あっちこっちしていると思われるかもしれませんが、患者さんの不調をたどっていくと、今の診察方法が適しているなと感じています。
そして、「自律神経」、「骨格(姿勢)」、「気象(気圧・温度・湿度)」という3つを、相互的にとらえていくことが大事だと考えております。
この3つを診察と治療に組み合わせていくことで、それなりの結果が出るようになりました。まだまだ勉強、研鑽、考察、研究ともになりないと自覚はしています。
いままで、いくつもの出版社の方々からお力を貸していただけたことで、「自律神経の書籍」、「気象病の書籍」、「背骨(骨格)の書籍」を出版することが出来ました。
2025年10月29水曜日に、東洋経済社さんから、新刊を発売させていただけることになりました。
自律神経、気象(気圧・湿度・気温)、骨格(姿勢)を3本柱とした、内容となっています。
今までの診療方針をまとめた感じのないように仕上げることが出来ました。患者さん、スタッフ、そのほか様々な方に支えられて、発売することが出来ました。ありがとうございます。
「自律神経 これ1冊ですべて整える」
www.amazon.co.jp/dp/4492048189
です。
出来るだけ、より多くの有益な情報をお伝えすることが出来たらと考えております。
前へ:« 2025・9 気象病が女性に多い理由は?―自律神経や女性ホルモンとの関係―
次へ:PIVOT さんから取材を受けました。前編 »
Blogメニュー
▶Blogトップ