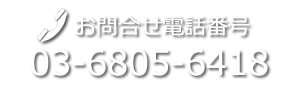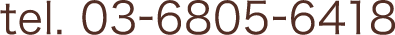首肩こりと不定愁訴-運動と漢方によるアプローチ②-
2025年5月8日 21:06更新
専門外来コラム
首肩こりと不定愁訴-運動と漢方によるアプローチ②-
前回のコラムでは、首肩こりの正体、そして首肩こりを引き起こす原因や生活習慣についてご紹介しました。では、自律神経失調症外来にいらっしゃる患者さんが首肩こりを解消すると、不調も一緒に改善していくのはなぜでしょうか?背骨や骨格のゆがみ、首肩こり(筋肉)、自律神経は、一見それぞれが独立した存在のように思われますが、実は関係し合っています。ストレートネックや猫背、反り腰など、程度の大小を考えなければ、骨格が乱れていない人はいません。特に首肩こりは日頃のセルフメンテナンスが結果として出やすい症状です。まずは自分の姿勢や骨格を知ることから始めてみましょう。
- 背骨は自律神経の通り道
背骨は、臼のような形をした小さな骨が連なって1本の背骨が構成されており、頚椎(首)・胸椎(胸)・腰椎(腰)・仙椎(お尻)と、部分によって名前がついています。特に、首には重要な神経がたくさん走っており、その中に自律神経も入っています。自律神経が通っているのは、背骨の中にある脊髄という場所です。交感神経は、胸髄(胸椎の部分)や腰髄(腰椎の部分)から出て背骨に沿うように走っており、副交感神経は、脳から首、腰のあたりから出ています。
背骨が歪んでいると、それだけ自律神経の通り道が妨げられてしまいます。背骨のゆがみが自律神経の不調の引きがねとなる理由の一つはここにあります。
- 首肩こり自律神経の不調や気象病との関係
[首肩こりによる血行不良が自律神経の働きを妨げる]
首こりで首の筋肉の血流が悪くなっていると、首を通っている副交感神経、そしてその先にある脳に十分な酸素や栄養が届かなくなってしまいます。その結果、副交感神経の働きを妨げることになります。また、肩・首・背中はさまざまな筋肉がつながってできているので、自覚の有無に関わらず、首が凝っていれば肩も凝っているでしょう。そして、背中の筋肉が緊張すると、そこから出ている交感神経に過度な刺激を与えてしまうかもしれません。
私は、気象病の対策を提案するのに、耳のマッサージだけではなく首や肩のストレッチもお勧めしています。自律神経が乱れている方は、それだけ気象病に対する耐性も低く、症状が出やすいです。首肩こりがあると自律神経の働きが低下するため、気象病を予防するためにも首肩こりのケアが必要なのです。
[呼吸への悪影響]
自律神経を整えるのにまず基本となるのが呼吸です。というのは、呼吸を整えることで、自ら交感神経と副交感神経を自分で調整することができるからです。息を吐くと副交感神経優位、息を吸うと交感神経優位に傾きます。自律神経が乱れて不調が出ている方は、大半が浅い呼吸をしており、本来の正しい呼吸ができていません。その原因の一つが、呼吸をするための筋群が凝り固まって動きが悪くなっているという点です。特に注目したいのは胸鎖乳突筋と斜角筋です。胸鎖乳突筋は耳の後ろから鎖骨にかけてつながっており、斜角筋は首の真横にあります。両者は息を吸うときに使う筋肉の一つで、硬くなると呼吸が浅くなります。ストレートネックなどで首や頭が前に出ている姿勢が続くと、これらの筋肉が硬くなり、呼吸のしづらい状態が当たり前になってしまいます。
- 首肩こりと漢方
首肩こりに効果的な漢方薬があるのをご存じでしょうか?葛根湯には、体を温め、冷えなどによる血行不良を改善するという効能があります。葛根湯といえば風邪のひきはじめに飲む印象が強いかもしれませんが、実は首肩こりにも使うことのできるお薬です。葛根湯には、クズ(葛根)、タイソウ、マオウ、カンゾウ、ケイヒ、シャクヤク、ショウキョウという生薬が含まれています。これらの成分が、体をじわじわと温め、特に頭や首周辺の筋肉の緊張を緩めてくれます。
私の外来では、首肩こりや体調不良が酷い患者さんに、セルフメンテナンスと併用して葛根湯を処方することがあります。漢方ではありませんが、首肩こりの症状や体調の重症度によっては筋弛緩薬やビタミン剤などを試すこともあります。
- 根本から治すなら脊椎全体を整える
首肩こりは日頃のメンテンナンスで差が出やすい場所です。いくら首肩を一生懸命ストレッチやマッサージをしても改善しない場合は、骨格のゆがみに理由があるかもしれません。
骨格のゆがみで代表的なのがストレートネックや猫背です。ストレートネックは、本来ゆるいカーブを描いているはずの頚椎がカーブを失ってまっすぐになっており、横から見ると、まっすぐ立っていても頭が前に出た姿勢になります。猫背は肩が内巻きになり(肩甲骨は外側に開いたような位置になります)、胸まわりの筋肉が硬くなっていることが多いです。胸椎の動きも悪くなっています。
土台である骨格が歪んでいると、自分にとって楽な姿勢をしているつもりでも、それを支える筋肉には負担がかかり、筋肉が伸びきって硬くなってしまっている可能性があります。そのような状態になってしまうと、凝っている部分をストレッチしただけではすぐに筋肉は元の血行不良の状態に戻ってしまいます。首は背骨の一部で下までつながっているので、背骨全体を整えて筋肉・骨格のメンテナンスをすることで、首肩こりを根本から改善することができます。急に背骨のケアと言われても難しいかもしれないので、まず基本として、「背骨の上に頭がポンっと乗っている感覚」というのを意識できることが大切です。
- まずは自分の姿勢を知ることから
ストレートネックや猫背、反り腰など、なんとなくは自覚していても、自分の背骨のカーブや動きの具合(可動域)がどの程度なのかを知る機会は少ないのではないかと思います。自分に必要な運動やメンテナンスをするために、まずはセルフチェックで自分の骨格について知りましょう。
[正面から縦の軸・横の軸のチェック]
身体のバランスを見るために、縦の軸と横の軸を考えます。鏡を見る前に3回ほど深呼吸をして力を抜きましょう。力んで姿勢を正そうとしてしまうと、普段の姿勢ではなくなってしまい評価がずれてしまいます。縦の軸とは、正面から見て眉間・アゴ・鎖骨と鎖骨の間、へそ、かかとの間の点を結んだ時の一本線です。背骨のラインも一緒にイメージできると良いでしょう。そして、横の軸とは、両耳をつないだ時にできる一本線です。その他にも、肩、骨盤、膝、くるぶしの位置もチェックすると良いと思います。
[壁を使って立ち方のチェック]
かかと、お尻、肩甲骨、の3点を壁に付けるように立ちましょう。力は抜いてリラックスした状態が好ましいです。見るべきポイントは2つです。
ⅰ壁に頭が付くか
ⅱ壁と腰の間にどのくらいすき間ができるか
大きくこの2点に分けて姿勢をチェックしてみましょう。頭は、後頭部が自然に壁に触れるのが理想的です。壁から離れてしまう方は、反り腰、猫背のどちらかの影響で頭の位置が前にずれてしまっているなどが疑われます。壁と腰の間のすき間は、壁と腰の間に指1本分のすき間ができる状態が理想です。すき間がこぶし1個分くらい空いている方は反り腰、逆にすき間がほぼできない方は猫背が強い可能性があります。背骨はお尻のあたりから1つずつ積みあがってS字にカーブを描いています。そのため、反り腰や猫背があると、首がバランスを取るために本来のカーブを無くします。こうしてできあがるのがストレートネックです。ストレートネックの方は、首だけが悪いというケースは少なく、反り腰や骨盤後傾、猫背など首より下の部分が大元の問題となっていることが多いです。
[頚椎(首)・肩・胸椎・腰・股関節]
ここまで読んで背骨全体を整える必要があるとわかって頂いた方は、背骨を頚椎(首)・肩・胸椎・腰・股関節に分けてメンテナンスをしてみましょう。細かく分けて評価をしてみると、自分の弱い部分、たとえば「胸椎が硬い」、「股関節の動きに左右差がある」などと気づくことができ、エクササイズも効果的に行うことができます。書籍「不調がデフォな私たちの背骨リセット」に詳細のチェック方法やエクササイズが載っていますので、これから小出しでご紹介していく予定です。
前へ:« 首肩こりと不定愁訴-運動と漢方によるアプローチ①-
次へ:2025・6 気象病による頭痛の特徴とその対策 »
Blogメニュー
▶Blogトップ