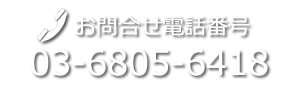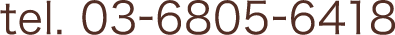気象病治療に効果のある五苓散の使い方
2025年7月4日 07:27更新
専門外来コラム
気象病治療に効果のある五苓散の使い方
日本の異常気象が進むにつれて、気圧や気温の大きな変化で体調を崩される方が増えました。気象病専門外来を始めて約9年経ちますが、年々、気象病の認知度が高まっていると感じています。気象病の治療薬として数年前から注目されているのが、五苓散という漢方薬です。昨年、学会誌で「気象変化に伴う頭痛に対する五苓散の有効性と安全性」という題目で論文を発表させて頂きました。気象変化によって体調不良を訴える患者さんが増加しているという現状もあり、気象病の治療や五苓散などに関心を持つ医師も多く、気象病治療の需要の高さを実感しています。
205/6/7には、日本東洋医学会総会にて、ランチョンセミナーで発表をさせて頂きました。800名以上の現地での参加者があり、気象病への認識の高さが強いと再認識しました。
今回のコラムでは、東洋医学における気象病の捉え方や五苓散についてご紹介していきます。
- 気象病は水滞によって起こる
東洋医学において、健康とは「気」、「血」、「水」のバランスが整っている状態と捉えます。そして、気と血と水のバランスが崩れたとき、不調が出ると考えます。気象病は、「水滞」といって「水」のバランスが崩れており、水の巡りが滞った状態です。「水」は血以外の体液のことを指し、組織液やリンパ液がそれに当たります。気圧の変化が起こると、体内で水の流れや水の状態に異常をきたし、気象病に特徴的な頭痛やめまい、倦怠感といった症状が出やすくなります。
- 「水」のバランスチェックをしてみましょう
「水」のバランスを見るために、以下の項目に当てはまるかどうかチェックしてみましょう。多く当てはまる方ほど体が水滞に偏った状態と言え、気象病の症状も出やすいです。
・浮腫みになりやすい
・天気が悪いと体調が優れない
・雨が降る前など、天気が変わることを予測できる
・めまいや耳鳴りが起こりやすい
・軟便・下痢ぎみ
・頭が重い
・体が重い
・車酔いしやすい
- 気象病の薬物治療は五苓散からスタート
[五苓散の効能]
五苓散という漢方は、体内の水分バランスを改善する代表的な利水薬です。副作用が少なく、飲みやすいのも特徴です。五苓散は、ソウジュツ、ブクリョウ、チョレイ、タクシャ、ケイヒという5つの生薬が配合された漢方です。五苓散には、体のむくみが取れて気象病の症状を和らげるはたらきがあります。気象病に限らず、頭痛やめまい、むくみ、二日酔いなどの改善にも広く用いられます。
[気象病での使い方]
気象病の方にまず私がお勧めする五苓散の飲み方は、定期投与です。定期投与というのは、1日2~3回、決まった時間に、一定期間飲み続けることを言います。飲み始めは体に溜まった余分な水分が排出されるので、尿がいつも以上に出たり、頻尿になったりすることがありますが、徐々に落ち着いてきます。一旦、水分バランスを整え、症状のコントロールがついてきたら、症状が出た時や気圧変化が大きい時だけ頓服で飲む方法にするのも良いでしょう。
- 論文「気象変化に伴う頭痛に対する五苓散の有用性と安全性」
先日、頭痛学会で五苓散に関する論文の発表をさせて頂きました。少しだけ内容をご紹介します。気象変化(気圧・寒暖差・湿度)に伴う頭痛に対する五苓散の有効性と安全性を目的とし、①気象病があり、気象変化に伴う頭痛がある②初診以降も来院している、これら2つの条件を満たしている患者さんを対象としています。
五苓散の投与方法は、7.5mgを1日2~3回、食前または食間に経口投与としました(患者さんの年齢や体重、症状により量は適宜増減)。その結果、1週間あたりの頭痛の回数、頭痛の程度、鎮痛薬の使用回数、すべてにおいて有意な減少が認められました。特に、痛みの程度に関してはほぼ半減したというデータが出ております。この研究から、五苓散は、気象病で頭痛を訴える患者さんにとって症状をやわらげ、QOLを上げるのに役立つ漢方薬であるということが明らかになりました。
- 漢方以外で水の巡りを改善する方法
五苓散で水滞が改善する方でも、可能であればお薬は最小限にしたいですよね。普段の生活で水の巡りを良くする習慣も大切にしていきましょう。
[運動]
運動は、血の巡りが良くなり老廃物が溜まりにくくなるため、体の余分な水分も溜まりにくくなります。特に、ウォーキングやジョギング、水泳などの有酸素運動は、全身の巡りが良くなり、むくみの予防・改善につながります。余分な水分は、重力に従って身体の下の方に溜まりやすいです。1日の終わりにふくらはぎをマッサージすると、疲労物質が血管に運ばれてむくみが改善されます。また、普段からストレッチの習慣や背骨を動かす運動(ヨガやピラティスなど)を継続していると、血行不良が起きにくい体になります。
[入浴]
入浴には、全身を温めて血流を改善する効果がありますが、静水圧作用といって、湯船の水圧が全身に加わることで血行を促進し、むくみを解消する効果もあります。身体に余分な水分が溜まっているということは、身体が冷えやすくなるということです。血流が悪くなり、身体に老廃物が溜まるため、入浴で日々の冷えをリセットすると良いでしょう。入浴は水の巡りに限らず、睡眠の質を上げたり、自律神経を整えたりと、さまざまな健康効果があります。
前へ:« 2025・6 気象病による頭痛の特徴とその対策
次へ:自律神経に優しい環境づくりと夏でもできるセルフケアー »
Blogメニュー
▶Blogトップ