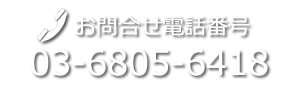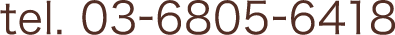自律神経と骨格①背骨のつくり
2024年5月10日 17:22更新
専門外来コラム
自律神経と骨格①背骨のつくり
自律神経失調症外来や気象病外来、頭痛外来など、せたがや内科・神経内科クリニックの専門外来では、骨格のゆがみや背骨に着目して治療を行っています。自律神経が大きく乱れている患者さんや不定愁訴(原因がわからない体調不良)を抱えている方は、骨格のゆがみが目立つ方が多いです。骨格は、誰しも多少は歪んでいるものなのですが、ゆがみが強くなり体のバランスが大きく乱れていくと、頭痛やめまいなどさまざまな不調を引き起こす原因となります。骨格において特に重要なのは背骨です。背骨は骨格を構成するうえで軸となり、重要な存在です。しかし、私たちが生活している中で、背骨を意識する機会は中々多くはないのではないかと思っています。今回のコラムでは骨格と背骨について書いていきましょう。
- 骨格の話
人間の体は200コ以上の骨でできています。骨格というのは、体にとって大切な土台です。骨は体を支えており、骨格を成すことによって複雑な動きを可能にしています。
骨格は軸骨格と付属肢骨格の2つに大別されています。軸骨格は頭蓋骨、背骨、肋骨、胸骨から成っており、体の中心を通る軸を作っています。一方で、付属肢骨格は四肢(両腕・両足・鎖骨・肩甲骨・骨盤など)で構成されており、軸骨格に四肢がくっついているようなイメージです。それらの中でも背骨は、軸骨格の主要な動きを作る重要な存在です。
おまけになりますが、骨格系には、体を支える(支持)、動かす(運動)だけではなく、保護、貯蔵、造血という役割もあります。保護は頭蓋骨や胸郭に当てはまり、脳や内臓などを守っています。貯蔵というのは、骨の中はカルシウムやリン酸、マグネシウムなどを蓄えて血液の中の成分を調整しています。さらに、造血は骨髄に該当します。骨髄では赤血球や白血球・血小板などの血液が造られています。
- 背骨のつくり
みなさんは、背骨と言ったらどこを想像するでしょうか?背中のあたりをイメージされるかもしれませんが、正確に位置を認識している人の方が少ないかもしれません。背骨は首から胸、腰、そしてお尻の部分まで繋がっています。
背骨というのは、医学・解剖学的に言うと「脊椎」という表現をします。首のあたりになるのが脊椎、胸のあたりが胸椎、背中・腰あたりが腰椎、その下が仙椎と言います。背骨は”1本”という呼び方をしますが、まっすぐ1本につながっているという訳ではありません。臼のような形をした小さい骨(椎骨)が縦に連なって構成されています。小さな骨と骨との間には椎間板というクッションの役割をしたものが挟まれています。一般的によく言う椎間板ヘルニアは、このクッション約の椎間板が飛び出てしまっている状態です。
背骨は頚椎、胸椎、腰椎、仙骨・尾骨が連なってできています。頚椎が7コ、胸椎が12コ、腰椎が5コ、仙骨(仙椎5コ)が1コ、尾骨が1コです。人間を横から見るとS字状のカーブを描くように重なっています。頚椎と腰椎は前にカーブ、それ以外の部位は後ろにカーブしてバランスを取っています。首の始まりの第一頚椎は鼻の奥あたり、背骨の一番下にある尾骨はお尻の割れ目の上のあたりです。意外と縦に長いですよね。
- 背骨の役割
背骨は骨格の中心にあり、姿勢をつくるうえでも軸となります。「骨格がゆがむ」とは、背骨がS字状に標準的なカーブを描いた状態から、カーブが強くなる、カーブが弱くなる、前から見て横方向に歪む(側弯と言います)など、正常なカーブを描かなくなることです。そもそも背骨がS字にカーブを描いているのは、頭や内臓を支え、体が動いた時の衝撃を吸収するためです。人間の体には、重力がかかっています。頭の重さは5~6kg、その重さを背骨1本で支えなければいけないため、背骨が弯曲することによって体のバランスを保っています。
皆さんは「背骨の動き」を意識したことがあるでしょうか?赤ちゃんの動きを想像してみてください。人間は、赤ん坊の段階では背骨の柔軟性が高く、動きもしなやかです。背中が丸まったり反ったりしても、大人と違って痛みやケガが出にくいでしょう。しかし、年齢を重ねるようになると圧倒的に増えるのが、座っている時間です。学校や会社に通うようになると、うつむき姿勢や背中が丸まった状態で何時間も作業をする…というような状況が容易に想像できますよね。このように悪い姿勢でいる時間が長くなると、骨格が歪んで姿勢が悪くなるだけではなく、その姿勢が癖になって固まってしまうので、背骨の動きもどんどん悪くなっていきます。運動の習慣が無い人は、前屈や後屈、側屈などの軽い伸びをするだけでも、体の動かしづらさを感じるでしょう。背骨が本来持っている役割も発揮しきれず、アンバランスになっていきます。
- 骨格が歪んでいる患者さんの特徴
自律神経失調症や気象病、その他原因不明の不定愁訴などを抱えている患者さんは、背骨がゆがんでいるケースが大半です。診察をしていて特徴的なのが、首肩こりが酷いのにも関わらずその自覚が無いということ。自分ではそこまで酷いとは思っていないため、セルフケアができていない方が多いです。そして、立って目を閉じて頂くと、フラフラで立っていられないほどのこともあります。普段は目で補正をしているのですが、骨格がゆがんで左右差があると体のバランスを取るのが難しくなっているのです。これがめまいの原因にもなります。骨格が歪んでいると、さまざまな不調を引き起こすため、背骨のケアはとても大切です。
春に起こりやすい不調・寒暖差疲労②対策
2024年4月10日 21:01更新
専門外来コラム
春に起こりやすい不調・寒暖差疲労②対策
先月のコラムでは、春に起こりやすい不調や寒暖差疲労についてお話しました。今年の春は、2月は季節外れの暖かさになったものの、3月に入ると中々気温が上がらず、春にしては気圧の上下や雨が多かったように思います。桜の開花も遅れましたね。目まぐるしく変わる気候に、すでに体調を崩してばかりの方も多いかもしれません。今回は春の不調の対策について書いていきます。
- 春の不調を乗り切るための対策は?
①不調の傾向を「なんとなく」把握する
春は本当に体調を崩す要素が多い季節です。体調が悪い時はさまざまな要因が重なっていることが大半ですが、気圧に弱い、寒暖差に弱いなど、人それぞれに傾向はありますよね。
自分の不調が何によって起きているのか、寒暖差や気圧、花粉など、自分が弱い気候変動やダメージを受けやすいストレスについて知っておきましょう。
たとえば寒暖差の影響を一番受けやすい方は、体温調節と冷え対策に焦点を置いた方が良いです。毎日欠かさずお風呂に入ったり服装に気を付けたりと、小さな工夫ができるだけでも体調への影響が変わってきます。また、気圧に弱い方は、気圧の予報を見てスケジュールを立てると体への負担を減らせるでしょう。
このように、ポイントなのは、自分の傾向を「なんとなく」把握するということです。あまり細かく考えてしまうと、環境の変化や不調に意識が行きすぎてストレスが増えてしまいますのでお勧めしません。「なんとなく」で良いので自分の取り扱いがわかってくると、不調がある中でも生活が楽になっていくと思います。
②寒暖差には服装調整と入浴で冷え対策
春の装いは華やかで素敵ですが、冬の装いから一転、急に肌の露出が増えたり薄手の生地の服になったりしますよね。確かに日中は暖かいので薄着で丁度良いこともありますが、夕方になると一気に冷え込むので、薄着のままでいると体が冷えてしまい寒暖差の影響をもろに受けてしまいます。
「服装の工夫でそこまで体調に影響するの?」と思う方もいるかもしれませんが、たとえば足首を出さないように工夫するだけでも体の冷え具合が違ってきます。冷えを我慢し続ける日々と、小さな冷え対策をつみ重ねた生活とでは、後々に感じる体調が変わってくるでしょう。
「首」をつく場所は太い血管が通っており、体の冷えに影響します。春の寒暖差で少し肌寒い時は手首・足首・首を冷やさないようにすると、体から出ていく熱が少なくて済みます。春はストールを1枚持っておくと便利ですね。
服装は冷えの予防に役立ちますが、もう一つ大切なのが入浴です。入浴は、1日に蓄積した冷えをリセットするイメージです。お風呂に入ることは、自律神経の調整、睡眠の質の向上、血流の改善、代謝のアップ、リラックスなどさまざまな効果があります。1日を頑張った最後にゆっくりお風呂に浸かることは当たり前のようで、心身の健康にとってとても有益な習慣ですよ。
③花粉症の方は我慢しすぎずに病院へ
そろそろピークを越してくる時期ですが、花粉症対策についてもご紹介します。花粉症の方は、毎日さまざまな症状が出ていると思います。花粉症で弱っている分だけエネルギーが消耗されているので、もちろん自律神経のキャパシティーも小さくなり、それ以外の不調も出やすい状態です。花粉症は薬である程度症状を軽くすることも可能なので、我慢しすぎずに早めに病院を頼ってみましょう。
④骨格のメンテナンスを習慣に
寒暖差疲労や気圧の上下により、自律神経は疲れきってしまっている状態です。みなさんは背骨の動きを意識したことがあるでしょうか?背骨は自律神経の通り道でもあるので、背骨のゆがみが少ないこと、背骨の柔軟性を高めることが、自律神経のはたらきにとって大切な2点です。背骨は姿勢の要となる存在で、背骨のゆがみが骨格や姿勢のゆがみをもたらします。以下、背骨のエクササイズをご紹介するのでぜひやってみましょう。
≪背骨の屈曲と伸展≫
※タオルを用意します。
ⅰタオルを横に長く持ちます。息を吐いて、みぞおちの辺りを思いきり凹ませるように背骨をC字に丸めます。両腕は前方向にパンチするように水平に保ちます。この時、呼吸は止めないこと。また、肩は力んで上がらないように力を抜きましょう。
ⅱ今度は息を吸って、手はバンザイをするように上へ。胸を開き背骨を少し反らせて伸びを感じましょう。
ⅰ、ⅱの動きを10回ほど。無理のない範囲で行いましょう。お腹の力が抜けてしまうと腰を痛めてしまう可能性があるので、ご注意ください。
≪背骨の側屈≫
タオルを横に長く持ちます。両腕を上げた状態で息を吸い、吐きながら右に体を傾けます。左の脇の下あたりが伸びるのを感じながら、背骨が上と下に引っ張られている感じも意識して傾けましょう。元に戻ったら今度は左も同様に行います。左右10回繰り返しましょう。
⑤寒暖差腰痛の対策
寒暖差腰痛についてもお話しました。
https://youtu.be/7Goh8G1EU1s?si=um5JRt3qexZq4jjc
提携先の賀来大樹さんの動画でも腰痛の対策について発信されていたので、ここにも載せておきます。寒暖差に限らず腰痛で悩まれている方は多いと思います。ぜひ参考にしてみてください。
春に起こりやすい不調・寒暖差疲労①
2024年3月12日 14:06更新
専門外来コラム
春に起こりやすい不調・寒暖差疲労①
今年度も終わりに差し掛かってきました。気温も少しずつ上がり、日差しの暖かさを感じるようになってきたと思います。春になると卒業式や入学式などの行事や、桜も咲き始めるのでお花見、おでかけなどの行楽イベントも増えますよね。せっかくなので元気に乗り越えたいところですが、春は寒暖差や気候変動が激しかったり花粉が飛んだり。自律神経が乱れやすく、体調にも負担のかかる季節でもあります。
今回のコラムでは、春に起こりやすい不調の特徴についてご紹介していきます。
- 春の気候の特徴
春の気候は、何と言っても寒暖差が大きく変化が起きやすいです。季節の変わり目なので、1日の気温差が大きいだけでなく、日によって冬に戻ったり夏寄りの気候になったりと、目まぐるしく気候が変動します。そして、風が強く空気が乾燥しています。昨年の春は「春の熱中症」が特集されていたくらいなので、目ぼしがつきにくい季節です。
暖かいと思ったら寒さを感じて体が冷えたり、乾燥で目や喉の調子が優れなかったりします。気圧も安定しないので、季節に体が馴染むまでが大変です。また、暖かさを感じる頃からスギ花粉や黄砂が飛び始めるので、気温、気圧、湿度、花粉など、さまざまな要因が重なると、心身にかかる負担が大きくなります。
- 春に起こりやすい不調は?
①寒暖差疲労・寒暖差アレルギー
寒暖差疲労とは、気温差によって起こるさまざまな不調のことをいいます。具体的には、疲労感、倦怠感、首肩こり、冷え性、咳や鼻水などのアレルギー症状、メンタルの不調などがあります。春は寒暖差が大きいので、専門外来でも、ぐったりと疲れてしまったり、なんとなく調子が出ないという方が増えてくる印象です。
人間の体は、どんな環境にいてもおよそ36℃~37℃くらいの平熱で保たれています。外の気温が上下した時は、環境の変化に対応するために自律神経が体温を調節するようにはたらきます。そのため寒暖差が続くと、体温を一定に保つために自律神経がたくさんはたらかなければいけないので、エネルギーが消耗されてしまいます。
②花粉症
春は花粉の季節ですね。3月はちょうどスギ花粉のピークに値する時期でしょう。花粉症は、花粉によって引き起こされるアレルギー症状のことを指します。症状は、鼻水、鼻づまり、くしゃみ、目のかゆみなどです。喘息やアトピー性皮膚炎につながることもあります。一般的には、スギ花粉・ヒノキ花粉による花粉症が多いです。人によってはブタクサやヨモギ、イネ科の植物など秋に飛散する花粉で症状が出る方もいます。
最近では、モーニングアタックと言って、朝早くの時間に花粉症の症状が強く出やすいことがわかっています。ウェザーニュースさんの調査によると、花粉症が辛い時間は、1位が14時頃、続いて2位が6~8時頃となっています。
朝目覚めたときは、副交感神経が優位な状態から、交感神経が優位な状態に切り替わる時間です。交感神経にスイッチが入るタイミングなので、鼻が刺激に過敏になっている時間帯でもあります。花粉を始め、布団や室内のハウスダストなども混ざって吸い込むことで花粉症の症状が出やすいです。
③メンタルの不調
自律神経はとにかく「変化に弱い」という性質を持っています。春は気候だけではなく、年度末・年始始めということもあり、卒業や転職、入学や就職、引っ越しなど環境の変化も大きいシーズンです。つまり、とても自律神経が乱れやすい状況にあります。また、寒い季節は交感神経が優位にはたらく量が多くなりやすいのですが、春になって急にあたたかさを感じるようになると、全体的に、日中でも副交感神経の活動が増えます。すると、心身にスイッチが入りにくくなり、怠さや元気の無さを感じやすくなります。
自律神経が乱れると心の面でも不安定になりやすいので、さまざまなストレスが積み重なって対処しきれなくなってくると、メンタルの不調も出てきます。感情がコントロールできない、無気力になってしまった、などという方は、心の問題だけでなく自律神経にも目を向けて対策をしてみましょう。
④肌トラブル
寒暖差や乾燥による肌へのストレスや、紫外線、花粉・黄砂などの刺激などによって、春は肌にとっても辛い季節です。自律神経が乱れていると、体の免疫機能が正常にはたらくことが難しくなり、肌荒れなどの肌トラブルが生じやすくなります。肌の調子は体の外側・内側どちらからもケアできるように意識した方が良いでしょう。
⑤腰痛
最近、寒暖差の影響で痛みが出る方が増えています。「寒暖差腰痛」と、呼ばれているようです。暖かいと何となく体の緊張が抜けていると思いますが、寒くなると体が縮こまりますよね。寒暖差に合わせて緊張したり緩んだりを繰り返すと、不意のタイミングで腰を痛めやすいです。特に今年は、寒暖差腰痛を訴える方が多くなっています。
自律神経は体温調節をするのに重要なはたらきをしており、寒暖差が大きい季節には自律神経が酷使されて乱れやすくなります。自律神経が乱れると、血流が悪くなるので冷えにつながります。血管が収縮し、筋肉が硬くなることによって末梢神経という神経が圧迫され、腰痛を引き起こすこともあるでしょう。特に日本は座りっぱなしの姿勢で過ごしている人が多いです。座っている方が腰への負担が大きくなるので、デスクワークの方は立ったり歩いたりする時間を積極的に取っていきたいものですね。
春は明るいイメージがありますが、健康面で考えると少し負担の大きいシーズンです。
「なんとなく」の不調がある方も、しっかり対策をして元気に過ごしたいですね。対策については次回のコラムでご紹介していきます。
寒暖差疲労の基本知識
2024年2月25日 23:01更新
専門外来コラム
≪寒暖差疲労の基本知識≫
最近は寒暖差が大きく、春めいてきたり極寒になったりと、季節がわからないような気候が続いておりますね。今年度は特に、年間を通して寒暖差が大きくなることが多かったと思います。ここ2~3年では「気象病」や「低気圧不調」などの気圧変動による体調不良が注目されるようになりましたが、少し遅れて「寒暖差疲労」というワードも広まりつつあると感じています。寒暖差による不調は今まではあまり知られていませんでした。しかし最近では取材を受ける回数も増え、少しずつ認知されてきているのではと思っています。
今回は寒暖差疲労の基本的な知識について書いていきます。
- 寒暖差疲労とは?
寒暖差疲労とは、気温の変化が原因で生じるさまざまな不調を言います。寒暖差というのは、1日のうちの最高気温・最低気温の差、前日との気温差、1週間単位での気温差、室内外(冷房の効きすぎた部屋やお風呂場など)での気温差などが当てはまります。目安ではありますが、1日の気温差が7℃以上になると不調が出やすいです。
寒暖差は私たちの体にとって大きなストレスであり、自律神経にも負担がかかります。そのため、体が寒暖差に適応しようとエネルギーを消耗、疲労が蓄積し、疲労感・倦怠感などを中心とした不調が出ます。寒暖差疲労以外にも、寒暖差アレルギーと言い、鼻水・くしゃみなどのアレルギー症状が出るものもあります。
- どんな症状?
気温差が大きくなると、自律神経が乱れます。寒暖差疲労の症状は、疲労感・倦怠感・だるさ、首肩こり、冷え、皮膚のかゆみ、めまい、気分の落ち込みなど様々あります。人によって出やすい症状が変わってくるので、寒暖差が原因であることに気づきにくいのも特徴です。
外気の激しい気温差により、体内の温度調整がうまくいかなくなっている状態なので、「顔は火照っているのに手足やお腹が冷えてしまっている」といったような現象が起きやすいです。冷えは万病の元というように、体が冷えてしまうと他の不定愁訴も連動して起こりやすくなります。不調が連鎖してしまうと辛いですよね。
寒暖差疲労と類似して、寒暖差アレルギーというものもあります。寒暖差アレルギーの症状は、くしゃみ、鼻水・鼻づまり、咳などです。この時期だと花粉症と間違われてしまうことも多いですが、花粉症とは違って目の症状(目のかゆみや充血など)が出にくいです。正式名称は血管運動性鼻炎と言います。
- 気をつけたい季節とシチュエーション
寒暖差が大きくなり、不調を感じやすいのは春・秋です。しかし最近では「季節外れの○○」という天候ばかりなので、1年中気にかけておいた方が良いかもしれませんね。
寒暖差の影響を受ける気温差の目安は7℃以上です。特に、暖かさ・寒さの両方を体感するような気温差が生じると、より寒暖差の影響を受けやすいと思います。どういうことかと言うと、同じ8℃差の日があった時、「8℃(最高気温)と0℃(最低気温)の日」・「20℃(最高気温)と12℃(最低気温)の日」では、後者の方が寒暖差を感じやすいということです。服装を変えなければいけないほどの差があるときは、寒暖差が大きいと考えた方が良いでしょう。
- 対策
①規則正しい生活
自律神経にとって、不規則な生活ほどダメージが大きいものはありません。自律神経の乱れで体を壊してしまう方は、交代制勤務のお仕事、働きすぎ、運動不足などが多いです。自律神経に負担のかかる生活をしていると、その分寒暖差による負荷にも弱くなってしまいます。基本的なことなのですが、規則正しい生活は丈夫な自律神経でいるためにはとても大切な習慣です。朝起きて日光を浴び、日中は適度に動き、夜になったら寝る、そして栄養バランスの良い食事を腹8分目、ストレスを溜めすぎず十分な休息を取る、といったように基本を意識してみましょう。
②脳腸相関
脳と腸が互いに影響し合っていることを、「脳腸相関」と言います。免疫系、内分泌系、神経系を介して、脳と腸はさまざまな情報交換を行っています。
腸の調子が良いと、その情報が脳に届くので、身体や心の調子も良くなるという訳です。腸が健康でいられれば、お腹の調子が良いだけでなく、自律神経をはじめ、心身のバランスも整っていきます。
ヨーグルトや味噌、納豆などの発酵食品などを取り入れる習慣がつくと、お腹も心も喜んでくれます。
即効性はないですが、続けていくと効果が出てきやすくなります。
③体温調節のできる服装
寒暖差が大きいと、朝晩と日中では適切な服装が変わってきます。無理して同じ服装でいると、昼間にのぼせて具合が悪くなったり、朝晩の冷え込みで体を冷やしてしまったりすることになります。寒暖差の大きいシーズンは、簡単に脱ぎ着できる服装を選ぶことを優先しましょう。また、汗を吸いやすい生地の服にすると、尚のこと快適に過ごせると思います。最近の天気予報では、気温に合ったおすすめの服装などが紹介されていますよね。何を着ようか迷った時は天気予報を参考にしてみてください。
④入浴で首まで浸かる
私は、寒暖差疲労の対策として入浴を推奨しています。入浴は日本人にとっては身近で当たり前のような習慣ですが、入浴にはさまざまな健康効果があります。寒暖差疲労では、体が冷えたりのぼせたりすることで、体内の熱の分布がおかしくなってしまっています。そこでお風呂にゆっくり浸かると、冷えて滞った血流が良くなり、全身が温まります。1日の冷えがリセットされているようなイメージです。
毎日シャワーで済ませてしまう人と、夜にお風呂に浸かってからぐっすり眠る人とでは、自律神経や冷えの面でも健康効果に大きな差が出ます。そして、「首まで浸かる」というのもポイントです。首には重要な神経がたくさん通っているので、自律神経を整えるのに大切な部分です。首を温めることでさらにリラックスができ、首肩こりも楽になります。
⑤首のストレッチ
最後に首のストレッチです。私たちの日常生活は基本的に下を向いている時間が長く、首に大きな負担がかかっています。そのため、日頃から首のストレッチを行ってケアをしてあげることが大切です。
※まずは長めのフェイスタオルを用意しましょう。
≪1≫両手でタオルを横に長く持つ。
≪2≫顔は正面を向いて、タオルの中心が首の付け根あたりに引っかかるように、ポジショニング。
≪3≫顔をやや上方向に向けて、タオルを持った両手は上向きに軽くテンションをかける。気持良いと思う程度の力で大丈夫です。このまま10秒キープ。呼吸は止めないこと。
≪4≫今度は下を向いて、タオルを持った手もやや下向きに力を入れる。こちらも強く引っ張り過ぎないこと。これも10秒キープ。
≪1≫~≪4≫を2・3セットほどできると良いと思います。
首は繊細な場所なので、くれぐれも力の入れすぎにはご注意ください。タオル1本で簡単にできるのでぜひやってみましょう。
自律神経失調症専門外来の提携トレーナー:賀来大樹さん
2023年12月3日 20:13更新
専門外来コラム
自律神経失調症専門外来の提携トレーナー:賀来大樹さん
今年は寒暖差が大きく、なかなか楽に過ごせるシーズンが少なかったですね。
久しぶりの専門外来コラムですが、今回はいつもとは違う内容を。
ある方のご紹介をしようと思います。
せたがや内科・神経内科の自律神経失調症外来・気象病外来・肩こり・首こり外来では、パーソナルトレーナーさんと提携して治療を行っています。患者さんの治療を行う上で大変力になって頂いているのが、賀来大樹(かくだいき)さんです。スタジオrenatoの代表をされています。今までは非公開だったのですが、彼がyoutubeで発信を始めてくれたので、ここでもご紹介しようと思います。
※気象病ハンドブックの後半にあるセルフケアの監修をしてくださった方です。
自律神経の不調や原因不明の体調不良でせたがや内科・神経内科を受診されている方は、骨格の歪みや筋肉の凝りが目立ちます。レントゲンを撮ると、反り腰や猫背、ストレートネック、側弯(背骨が横に曲がっている)などを持っている方が大半です。
骨格の歪みが少なからず不調に影響を与えているので、すぐに骨格の矯正でもできたら良いのですが、残念ながら今の医療では、骨格の歪みそのものを治す手段が存在しません。
私の話になりますが、開業当初は、私自身が患者さんにストレッチや運動の指導をしておりました。しかし、それだけでは「根本から治すことができない」という壁にぶつかり、整骨院や鍼灸、理学療法、カイロなどの専門家と連携してみましたが、患者さんの不調が完全に無くなる訳ではありませんでした。症状は大きく改善はしますが、しばらく経つと戻ってしまうという傾向がありました(戻る割合が多かったのです)。
そこで、パーソナルトレーナーである賀来さんとの出会いが大きな転機となります。パーソナルトレーナーのお仕事は、アスリートなどのパフォーマンス向上や、クライアントのボディメイク、健康増進など多岐に渡りますが、賀来さんには、運動療法と称して患者さんの骨格のコンディショニングを主にお願いしています。
運動療法の中には、皆さんがご想像するようないわゆる筋力系のトレーニングもありますが、それだけではなく、ピラティスや整体なども手段の一つとして取り入れているようです。
運動が体にとって良いことだ、というのは1人の人としても医師としても知っていたつもりでしたが、彼と出会ってから、運動が思っていたよりもずっと奥が深く繊細な領域だと知りました。患者さん一人ひとりの症状に合わせて治療を行うように、運動にも一人ひとりに合わせた処方のようなものがあるのですね。詳しくは気象病ハンドブックのコラムに書いていますのでぜひ。
医師としては、患者さんを問診や不調の全体像を把握、レントゲンや他の検査で骨格を評価、お薬が必要な場合は薬の処方、などをしています。私が呼吸の方法や簡単なストレッチ、生活習慣などの指導をして、改善がどうしても難しい場合は、賀来さんにご紹介することになっています。
彼がみることのできるお客さんの枠が少ないため、正直、患者さん全員をご紹介するのが難しい状況でした。今回動画で発信をされるというお話を聞いて、今までより多くの患者さんに正しいセルフケアの方法を届けられるようになることがうれしいですね。
私自身も賀来さんに身体をみて頂いているのですが、おかげで首肩こりや身体の不調がリセットされ、山積みの仕事をなんとかこなすことができています。
***
動画の概要です。
第1回のテーマは
「ストレートネックや肩こり等の不調が治らない理由と7つの改善エクササイズ」
せたがや内科・神経内科にも首肩こり外来があるように、肩こりに悩んでいる方はたくさんいると思います。肩こり対策の本や動画も数多く発信されていますよね。
色々試してみるものの、みなさんの中には「一時的にしか効果が無かった」、「あまり良くなった感じがしない」、という経験をされたことがある方は少なくないと思います。
「筋肉の凝り=ほぐす」という印象があるかもしれません。しかし、肩が凝っているからと言ってただストレッチだけをすればよい、という訳ではないのが実情です。(私もこれを知った時には驚きました。)
人によって原因がさまざまなので、根本を解決するためには、まず自分の心身の状態を把握することが大切です。それを評価と呼んでいます。自分の身体がどれだけ動くのか、どれだけ身体が緊張しているのかなど、意外と知らないものですよね。
この動画では、肩こりが中々治らない原因や、簡単な評価の方法が紹介されています。自分の身体を知っていくことから始めましょう。
個人的には、さまざまな根拠が説明してあり、骨格の絵や矢印がわかりやすいので、「なぜこの不調にこの運動が良いの?」という疑問を持たれている方にぜひお勧めしたいです。
クリニックにいらした患者さんにも、セルフケアの参考としてお勧めしていこうと思います。
気象病とアロマ
2023年1月19日 22:29更新
専門外来コラム
⑪気象病とアロマ
今回は気象病とアロマのお話です。
気象病や自律神経の不調にアロマが効果的なのはご存じでしょうか?
気象病は、気圧や気温・湿度などの変化によりさまざまな不調を引き起こします。気象変化が大きいと、それに合わせるように自律神経も乱れ、心身ともに調子が上がりづらいです。頭痛やめまい・倦怠感などの症状に加えて、気分が上がらずに寝込んでしまう方も少なくありません。
対処法や予防法はたくさんありますが、アロマは手軽に取り入れられるセルフケア方法の一つです。アロマには、体のバランスを回復させて心身をリフレッシュ・リラックスする効果があります。自律神経系・ホルモン系・免疫系を全体的に整えてくれるため、日々の健康維持や、生活を豊かにするアイテムとして、知っておくと良いですね。
・アロマオイルの持つ力
≪現代医学との違い≫
現代医学による投薬治療は、病気の治療には無くてはならないものですよね。しかし、薬というのは人工的で、作用が単一的です。一つの標的に対して集中的にはたらく強さがあるため、効果は大きいのですが、「必要な時に必要な分だけ」という使い方が理想です。
一方で、アロマは天然由来です。自然のものであるため、体にも容易に代謝・吸収されますが、それゆえ体内に残る時間も短いです。薬のような劇的な効果は見込めないかもしれませんが、薬よりも多様な成分が含まれているため、作用が全体的です。そのため、アロマは自律神経やホルモン・免疫系をバランスよく整えるのに適しており、日々の生活に継続的に取り入れることができます。
≪香りによる情報伝達≫
薬にはないアロマ特有の作用が、「香り」です。香りの情報は、嗅神経を通じて、自律神経をつかさどる視床下部・大脳辺縁系に伝わります。香りそのものによって、自律神経に関わる部分に作用し、ホメオスタシスを高めることができます。その結果、自然治癒力が上がります。
また、香りには、心に作用して記憶に残す力もあります。心と体はつながっているため、気象病で自律神経が乱れていると、どちらの調子も悪い方向へ向かいやすいです。そこで、心と体のバランスを整え、私たちをリフレッシュ・リラックスに導くのが香りの力です。自分の体調や好みによって精油を変えられるのも、良いポイントだと思います。
・アロマオイルと自律神経の関係
アロマの強みは、嗅覚を通して直接脳に作用する点です。アロマオイルの香りは、鼻から、
鼻の奥の鼻粘膜という場所を通過し、脳にたどり着きます。脳の中では、大脳辺縁系→偏桃体→視床下部の順に香りの情報が伝わり、自律神経系や内分泌系(ホルモン)、免疫系にはたらきかけます。
自律神経はストレスの影響を多く受けています。ストレスというのは、精神的なストレスから始まり、不規則な生活習慣や肉体的な疲労、環境条件など幅広く存在しています。気圧変化や寒暖差などの気象変化も立派なストレスの一つですよね。
自律神経は、脳の視床下部という場所が司令塔になり、心身のバランスを保っています。そのため、アロマの香りを通じて直接脳に情報が届くと、自律神経のコンディションを整え体と心の調子を改善することにつながります。
アロマは香りを鼻から楽しむ印象がありますが、一方で、皮膚に付けて吸収することもできます。皮膚に精油を塗る場合、精油の成分は直接皮膚から血流へ行き、同時に鼻から血流へ行き、体内に取り込まれます。また、「触れる」という行為は自律神経に良いため、ゆっくりと優しいタッチングをすることで、愛情ホルモンであるオキシトシンの分泌を促し、心と体が安心します。安心は、心身をつかさどっている自律神経にはとても大切な要素です。
・気象病に効果的なアロマブレンド
日本アロマ協会(AEAJ)によって考案された、「気候別のアロマブレンド」というものがあります。今回は、雨の日用のブレンドをご紹介します。
雨の日は副交感神経が優位になり、心身が休息モードになるため、体がだるくなったり元気が出ない傾向にあります。そこで、交感神経を優位にし、やる気をアップさせてくれる効果のあるオイルを選ぶと良いでしょう。
≪雨の日ブレンド:グレープフルーツ+スイートマジョラム≫
グレープフルーツ:
グレープフルーツには、交感神経に働きかけて血流の増加や気分を向上させる作用があるため、作業の効率が上がるでしょう。心に軽やかさをもたらし、リラックスというよりはリフレッシュしたい時に推奨されます。
スイートマジョラム:
スイートマジョラムは消化器をサポートするハーブで、昔からよく料理に使用されてきました。肉体的にも精神的にも温める作用があり、肉体的には冷えやむくみ、肩こり、消化器症状を改善し、精神的には緊張を緩和して孤独や悲しみを癒すと言われています。
・初心者の方はラベンダーから
ラベンダーは、リラックスの代表と言われており、万能でスタンダードな精油です。「アロマに慣れていなくてどの精油を選んで良いかわからない」という方にお勧めしています。ラベンダーは心身をバランスの取れた状態にするため、日常使いや、眠れない夜などに使うと良いでしょう。
・その他気象病・首肩こりに効果的な精油
バジル:疲れや痛みに効果があります。気象病による片頭痛・消化器の不調などがあるとき、自律神経の調整作用により心身をリフレッシュさせてくれます。
レモン:血流が良くなり、心身に爽快感をもたらしたり、集中力があがったりします。気象病や首肩こりなどで気力も体力も滞ってしまう時に、すっきりできる精油です。
イランイラン:バランス力が一番と言われている精油です。神経を落ち着かせて緊張や不安を軽減します。ストレスが溜まっていると感じる方は試してみると良いかもしれません。
≪参考文献≫
川口三枝子.「すぐ使えるアロマの化学 自律神経系 ホルモン系 免疫系の不調を改善!」BABジャパン.2020
気象病③ 寒暖差疲労・寒暖差アレルギー
2022年11月26日 13:02更新
専門外来コラム
気象病③ 寒暖差疲労・寒暖差アレルギー
最近は急に寒くなったり、突如ぽかぽか日和になったりと、1日の間や前日との気温差が大きくなっています。寒暖差疲労専門外来では、10月・11月にかけて、寒暖差による不調を訴える患者さんが多かったです。今年は特に患者さんが2倍ほど増えており、テレビや雑誌などの取材も例年以上と感じております。「寒暖差疲労」という言葉も少しずつ広まってきていますね。一般的には、気象病は低気圧(気圧の上下)のイメージがありますが、気温の上下、つまり寒暖差で起こる不調も気象病に当てはまります。
・寒暖差疲労とは?
急激な気温の変化が繰り返されると、体温調節をするために自律神経の乱れが激しくなります。自律神経は心身の働きに関与している重要な神経であるため、自律神経が酷使されると心身のエネルギーも消耗されます。それによって疲労感・倦怠感、頭痛、冷え性、首肩こりなどの不調が生じることを「寒暖差疲労」と言います。
寒暖差には、以下の3つのパターンがあります。
①1日のうちに起こる最低・最高気温の差
②前日と当日、週単位での寒暖差
③室内外の寒暖差(冷暖房・電車なども)
寒暖差は常に生じていますが、基本的には7℃以上の温度差があると不調が出やすくなります。春や秋は1日の気温差が10℃以上になることも少なくないので、注意が必要です。症状のうち最も訴えが多いのは疲労感・倦怠感、次は冷え・首肩こり、その次は頭痛・めまいです。
・寒暖差アレルギー
急激な気温差によって、アレルギーのような症状が出ることもあります。具体的には鼻水、鼻づまり、咳、くしゃみなど、アレルギー性鼻炎によく似ており、これを「寒暖差アレルギー」といわれています。
自律神経は血管の拡張・収縮に関係しているのをご存じでしょうか。鼻にたくさん通っている毛細血管が、気温差の大きい環境に対応しきれず血管の調整がうまくいかないため、症状として現れます。また寒暖差に限らず、季節の変わり目は気候の変動が激しく気道が過敏になりやすいので、呼吸器が弱い方や喘息持ちの方は調子が悪くなりやすいです。今年は、寒暖差による鼻水や咳などの風邪・アレルギー症状を訴える方が多かったです。
・気温の変化と自律神経の関係
人間の体温は、外の気温に関係なく36℃~37℃程度で一定に保たれています。これは、外気温の変化に応じて体の熱を産生していたり、逆に熱を放出したりして体温を調節しているためです。寒さや暑さは皮膚を通して感じますよね。その情報は脳の視床下部という場所の体温調節中枢に伝えられ、自律神経系や内分泌系、体性神経系を介して熱の産生と放出のバランスを取っています。ホメオスタシスを維持するために自律神経が微調整を担当して体温調節しています。
たとえば気温が上昇して暑さを感じると、以下の現象が起こります。
副交感神経による血管収縮能が抑えられ、血管が拡張して、皮膚表面での熱交換が行われる。
↓
それで体温上昇に対応的ない時には、発汗が起こる。発汗時の気化熱にて、体温を下げる。
↓
「発汗=水分の排泄」となるため、バソプレシン(詳しく調べる)というホルモンが増え、尿排泄量が減る。
**
反対に、気温が低下して寒さを感じた時は、以下の通りです。
交感神経により皮膚の血管が収縮、体表から熱が逃げていくのを防ぐ
↓
交感神経の作用により、副腎皮質ホルモン(アドレナリン)、甲状腺ホルモンの分泌が増える
↓
内臓で熱が作られる(新生児の場合は褐色細胞組織での熱産生も高まる)
↓
「ふるえ」を起こして熱の産生を増やす
寒暖差が大きいと、上記の微調整を繰り返す必要があり、自律神経が乱れやすくなります。
・寒暖差に対するセルフケア
寒暖差が大きくなると、日中は暖かいですが朝晩は冷え込みが強まりますよね。体が冷えると、血流が悪くなり、体の機能が低下してさまざまな不定愁訴が出やすくなります。寒暖差によって外気が寒くなったときは、必要以上に体を冷やさないことが大切です。
≪自律神経に効果的な入浴法≫
体を温めるための基本は、入浴でゆっくり体を温めることです。夏はシャワーで済ませてしまう方も多いと思いますが、秋に向けてお風呂に入る習慣をつけてみましょう。冷え性や自律神経の不調をお持ちの方、女性などには、エプソムソルトや炭酸風呂などをお勧めしています。
エプソムソルトにはマグネシウムが多く含まれており、リラックス効果や筋肉を緩める作用が、緊張した体をほぐしてくれます。マグネシウムは皮膚からの吸収が良いため入浴剤でも効率よく体内に取り込むことが可能です。自律神経の不調を抱える方には手軽に取り入れてみて頂きたいものの一つです。一方、炭酸風呂は、炭酸ガスが吸収されることで血管が広がり、体温が上がります。こちらも血行が良くなるので冷え対策に役立ちます。
お風呂に入っているときは、首まで浸かり、余裕があればふくらはぎや鎖骨下のマッサージをすると良いと思います。もちろん、ぼーっとリラックスしても大丈夫です。首には人間にとって大切な大きい血管や自律神経の通り道があります。首を温めて首肩こりを改善すると、全身の血流アップにつながりますし、自律神経のケアができます。
たとえば頚椎1番(首の付け根・耳や鼻と並ぶ位置にあります)を意識して「うん、うん」と頷くように首を縦に動かす(10~20回ほど)、次に頚椎2番を意識して横に首を振るように動かすと(同じくらいの回数)、普段は固まりやすい首の骨や筋肉の動きがよくなり、凝りが改善します。頭痛予防にもなるので、お風呂で時間のあるときにやってみましょう。
≪服装の工夫≫
寒暖差に応じた衣服の調整は、一般的にも言われていることですが、ポイントを知っておくとより効果的に体温調整できると思います。私がおすすめしているのは、マフラーやネックウォーマー、レッグウォーマー、腹巻・ホットパンツの3つです。太い血管の通り道である首・手首・足首、内臓が集中しているお腹を冷やさないようにしましょう。3つの中で意外と薄着になっている場所が足首です。足首が硬い方や足首を露出した恰好をすることが多い方は、冷えを引き起こしやすいです。デスクワークが多い方はぜひレッグウォーマーも活用してみましょう。
体が冷えすぎている方は、冷え症状と一緒にのぼせの症状も出る場合があります。「冷え性なのにのぼせもある」という方は、体の芯は冷えているのに頭や体の表面だけが暑くなっている方が多いです。のぼせてしまった場合は、頭や頬、手のひらなどを一時的に冷やすと、こもった熱が出ていきます。
参考:鈴木郁子(編著).やさしい自律神経生理学 命を支える仕組み.中外医学社.2015
「気象病ハンドブック」増版となりました
2022年10月22日 19:47更新
専門外来コラム
「気象病ハンドブック」増版となりました。ありがとうございます。
9/5に発刊となりました書籍「気象病ハンドブック」の増版が決定しました。今年の9月は台風が数多く発生し、複数の台風に囲まれたり勢力が史上最大級だったりと、気象病の方でなくても体と心に負担の多いシーズンでしたね。また、寒暖差による不調を訴える方も注目されてきており、気象病には気圧・気温・湿度の3要素が重要なポイントであると再認識しています。書籍を手に取ってくださった方には、
・セルフケアがたくさんあってありがたい
・気象病でなくても健康に関心のある人には役立つ
・ストレッチなどが新しい
・かわいい、さわり心地が良い、大切にしたくなる
などと声を頂きありがたい限りです。増版の知らせを聞き、出版社である誠文堂新光社の編集の方や製作スタッフ陣と喜びを噛みしめているところでした。
気象病ハンドブックは、さまざまな方にとって意義のある本になるように作られています。今回は、この本の使い方について用途別にご紹介します。
ⅰ気象病ハンドブックが活躍する場面
①気圧変動が大きい台風・梅雨シーズン
気象病で最も多いのが、気圧の変化による不調です。低気圧不調と言われているくらいなので気圧が下がるときに不調が出る方は多いですが、基本的には上下に関係なく、気圧の変化が起こると体調に影響が出ます。
気圧の低下・上昇が大きく繰り返されるのが梅雨・台風シーズンです。梅雨は雨の日が多くなるので、気圧が下がったり戻ったりと気圧変動が繰り返されると不調が起きやすくなります。また、梅雨時期は常に湿度が高いです。湿度の高さにより体温調節がしにくくなったり呼吸がしづらくなったりして、自律神経の負荷が増えます。
台風シーズンは気圧低下の程度が大きくなるため、不調もより強く出やすいです。台風の場合は、台風が遠くに存在していたとしても頭痛や倦怠感などが発症しやすいです。台風が過ぎ去ったと思うとまた発生して…の繰り返しが起こると、患者さんの心も折れてしまうみたいです。少しでもお薬やセルフケアで対策をすることが大切です。
②寒暖差の大きい春・秋
気象病は気圧の影響、という印象が大きいかもしれませんが、寒暖差による不調(寒暖差疲労・寒暖差アレルギー)にも注意しておきたいです。実際、最近では寒暖差による不調を訴える方も増えてきており、患者さんやメディアの取材・特集などが多いです。
寒暖差の大きい季節は春と秋です。寒暖差でポイントとなるのが、①1日の気温差②前日との気温差③室内外での気温差、の3つです。春と秋は①②の影響が大きく、疲労感や倦怠感、首肩こり、冷え・のぼせ、頭痛、めまいなどを訴える方が増えます。
人間の体温は、外の環境変化に影響されることなく、常に36℃程度で一定に保たれています。体温が一定でいられるのは、自律神経がはたらいて体温を微調整しているおかげです。寒暖差が大きければ大きいほど、体温調節に自律神経が酷使されることになります。必要以上に心身のエネルギーが体温調節に使われてしまうため、疲労感などが起きやすいのです。寒暖差のシーズンは、十分な休息と栄養補給、冷え・のぼせ対策がポイントになります。
③日頃から(自律神経や体のメンテナンスをしたい方)
現代は、心身に負担のかかるような多くのストレッサーが潜んでおり、自律神経が乱れていない人の方が珍しいですね。私のクリニックには、自律神経の不調により生活に支障が出ている方が多く来院されます。しかし本当は、不調が出る前に自律神経のメンテナンスをすることがとても大切です。生活習慣を整える工夫をするだけでも自律神経への負担を減らすことができるので、ストレッチや運動などをやってみましょう。
ⅱ目的別の使い方
①不調の知識を深めたい人は最初から1項目ずつ
気象病の対策は、お薬などの治療もありますが、セルフケアの部分が大きいです。ご自身で生活を見直すためには、「なぜ不調が起きているのか?」という根拠や仕組みを理解してからだと、より効果的にセルフケアに取り組むことができます。前半は、気象病の導入から気象病の正体、自律神経についてなど、学習要素が盛りだくさんです。まずはゆっくり勉強して知識を深めていきたいという方は、はじめから1項目ずつ読まれることをお勧めします。
②興味のある内容だけを知りたい人は好きなところだけを
気象病ハンドブックは、読者の方の疑問に応える形で、見開き2ページずつの構成になっています。目次を読んで、気になる内容だけを抽出して読むことができます。最初からじっくりよむ時間や体力がない方は、お好きなところだけ目を通して頂ければ大丈夫です。
③今ある不調を何とかしたい方は5章から
第5章は、気象病の症状別に、症状の特徴や対策を載せています。「今○○の症状があるから、今すぐ何とかしたい」という方は、まずはご自身の不調の項を読んで頂けたらと思います。ここだけのお話ですが、不調別にセルフケアや対策を載せたものの、他の症状にも効くストレッチや、合わせてやった方が効果的な内容もあります。たとえば、呼吸は自律神経を整えるための基本となるので、すべての症状に関係してきます。症状にお困りの方は、余力があるときに5・6章全体を見て頂けたら幸いです。
④不調はなくても運動習慣を見直したい方は6章を実践
6章は、気象病の不調を抱えている方はもちろん、より健康を目指したい方にとっても大切な運動・セルフケアが載っています。「気象病はそこまで重くないけれど、骨格を見直して適切な運動習慣を取り入れたい」という方は、6章だけでも構いません。私が推奨しているのは、主に背骨(肩甲骨や骨盤なども)を動かす運動です。背骨の動きが良い人は、心身の出すパフォーマンスが上がります。背骨は自律神経や髄液の分布とも関係しています。ご自身に本来備わっている能力を最大限に発揮することは、つまり不調が少なく元気に過ごすことにつながります。不調の方にも、より元気な状態を目指したい方にも、6章のセルフケアは必要ということですね。
気象病②ー自律神経との関係ー
2022年9月18日 21:22更新
専門外来コラム
気象病②ー自律神経との関係ー
せたがや内科・神経内科クリニックの専門外来では、気象病外来の他に、自律神経失調症外来もあります。気象病は自律神経のはたらきと関係している点が多く、2つの専門外来を同時に受診される方も少なくありません。自律神経を整える生活の工夫をしていくと、気象病の予防や改善にもつながります。先日の「気象病①」の記事は気象病の導入でしたが、今回は気象病と自律神経の関係についてお話していきます。
ⅰ気象病のメカニズム
・気圧に反応するのは内耳
地球上には、大気圧というものがあります。大気圧というのは、地球を覆っている空気による圧力のことで、人間の体は常にこの圧力を受けて生活しています。数値で示すととても大きな圧力なのですが(10t/㎥)、私たち人間の体が潰れてしまうことはありません。なぜなら、大気圧に対して体内からも同じ分だけ押し返す力がはたらいており、私たちは体感としての影響を受けることがないからです。特に負担などを感じることはありません。
しかし体に負担を感じないのは、気圧がある程度一定である時の場合であり、「気圧変動」が起きたときは違います。たとえば、飛行機に乗った時にお菓子の袋がパンパンになると言われていたり、耳が詰まったような感覚になったりするかと思います。このように、気圧が大きく変化する(上がる・下がる)と、体にも変化が生じます。
気圧の変化を感じるセンサーとなるのは、「内耳」という部分です。耳の鼓膜の奥に位置しています。先ほどの例にもありましたが、飛行機やエレベーターなどで体にかかる圧が変動すると、耳が痛くなったり・こもったりすると思います。これは鼓膜の内側が膨らんでいることによって生じる症状です。内耳で気圧の低下を感じ取ると、それが脳に伝わり、自律神経にも影響が加わります。気象病でめまい(一般的には耳鼻科の症状です)が出るのは、平衡感覚を担っている内耳と関係しています。
・体温調整と関係している自律神経
気象病は、気圧の変化だけでなく、気温や湿度の変化によって不調が起こることもあります。私たちの体温は、発熱していない限りは36~37℃程度で常に一定ですよね。外の温度に限らず体温を一定に保つことができるのは、ホメオスタシス(恒常性)と言って、体の状態を一定の状態(体温・血圧・電解質など)に保つことのできる人間の特性です(参照:コラム/自律神経とホメオスタシス)。
ホメオスタシスを維持するために重要な役割を果たしているのが、自律神経です。自律神経が体のあらゆる条件を微調整していることによって、ホメオスタシスが維持できます。体温で言うと、暑いと汗をかき、寒いと縮こまりますよね。暑さに関しては、末梢血管を拡張したり、汗をかいて体温が下がるようにし、寒さに関しては熱が奪われ過ぎないように末梢血管や筋肉を収縮して熱を産生します。これらの過程には常に自律神経のはたらきが関わっており、寒暖差が大きいと自律神経に負担がかかることになります。
・寒暖差疲労と寒暖差アレルギー
寒暖差によって起こる不調は疲労感とアレルギー様症状です。一般的には、7℃以上の寒暖差があると不調が出やすくなります。寒暖差に合わせて体温調整をするのに、自律神経が酷使されるためです。寒暖差による不調に注意したいのが冬から春にかけて暖かくなる3~4月、秋から冬にかけて寒くなる9月~12月あたりです。衣服による体温調整や冷え・のぼせ対策や環境調整をすることで症状を緩和することができます。
ⅱ気象病と自律神経失調症の違いは?
- 気象病
:気圧や気温の変化(寒暖差)、湿度などの気象条件が変化することによって、心身ともにさまざまな不調が出ることを言います。
- 自律神経失調症
:心身の調子を整えている自律神経のはたらきがうまくいかず、交感神経と副交感神経のスイッチングが適切にできなくなります。それによって出るさまざまな不調(倦怠感、首肩こり、頭痛、めまい、動悸、息切れ、低血圧、胃腸障害、不眠、抑うつなど、自律神経症状と言われているもの)が起こることを言います。
これらの不調に関して、必要な検査を行ない原因が特定されない場合に、自律神経失調症の可能性が高くなります。
気象病と自律神経失調症は似ている部分も多く、関係が深いです。気象病の症状は多岐にわたり、人それぞれ訴える症状が異なりますが、これは気象病が与える自律神経への影響が大きいためです。気象変化によって不調が起きると自律神経の乱れが起きていますし、逆に自律神経が乱れている方は、気象変化に弱く気象病を発症しやすいです。
ⅲ気象病の方は自律神経を整える工夫を
先ほど述べたように、気象病は自律神経との関係が深く、自律神経が乱れている方ほど気象病になりやすいと言えます。自律神経が整っている方は、日常にあるさまざまなストレス(身体・精神・環境など)に耐える受け皿が大きいです。そのため、気圧低下や寒暖差によるストレスが加わったとしても、不調になることなくストレスを乗り越えることができます。しかし自律神経が乱れている方は、はじめから心身ともにストレス耐性が弱くなっている状態です。気象変化に対応するだけのエネルギーが足りず、容量を超えた分だけ不調が出てしまいます。
自律神経は日常生活の工夫やセルフケアによって、整えることができるものです。特効薬のようなものはありませんが、自律神経失調症で不調が慢性化してしまった方でも、生活習慣を変えていくことで具合の悪さを少しでも和らげることが可能です。自律神経に関心を持ち、心と身体を大切にする習慣を作っていくことから始めると良いですね。不調は辛いですが、あまり神経質になり過ぎないことがポイントです。
書籍「気象病ハンドブック」9月発売に向けて
2022年7月16日 19:23更新
専門外来コラム
今年は空梅雨でしたが、猛暑になったり大気が不安定だったりと、体に負担がかかる天気が続いていますね。
一部SNSでは公開いたしましたが、実は今、2022年9月発売に向けて「気象病ハンドブック」という本の執筆に取り組んでいます。
この本は、気象病に悩む方はもちろん、気象の変化でなんとなく調子が上がらない方・雨の日でももっと元気に過ごしたい方など、さまざまな方にとってお役に立つ本となるように力を注いでいるところです。
手に取って頂けたら嬉しいですが、その前に、どんな本なのかだけでも知っていただけたらと思います。そこで、今回は「気象病ハンドブック」のご紹介と製作の裏話などを含めてお話させていただきます。
- 「気象病ハンドブック」が気象病のバイブル本となるように…
「この1冊があれば、気象病のすべてがわかる——」
そんな本を目指して、「気象病ハンドブック」というタイトルを付けました。
現在、完成に近づいてきましたが、まさにタイトル通りのものが出来上がっていると思います。
最近では、「気象病」や「自律神経」という言葉が以前よりも普及してきたと肌で感じています。気象病専門外来を設立して約 6年になりますが、今まで気象病に悩みながら、周囲に理解されないことにも苦しむ患者さんを多く診てきました。気象病はきちんと原因がある不調ですし、原因があれば対策もあります。「気象病がやっと認知されてきた」という気持ちは大きいです。
気象病とは、気象条件の変化(気圧や気温・湿度など)によって起こる心身の不調のことを言
います。最近では気圧を予測するアプリや気圧予報などが多く見られるようになりました。それだけニーズがあるということですね。気象病に特徴的な症状は頭痛や倦怠感・めまいなどですが、症状は本当に人それぞれです。
オンライン診察も一般的になり、気象病専門外来も全国から患者さんが診察にいらっしゃいます。しかし、私の診察時間にも限界がありお伝えしきれないことも多くあります。また、「病院に行くのは気が引けるけれど、気象の変化で何となく不調がある」という方などにも気象病との付き合い方やセルフケアをお伝えすることで、多くの方々が天気に左右されることなく元気に過ごせるように、本を書きたいと思いました。
- 気象病のすべてが詰まっています
私が大切にしているのは、「健康をトータルで考える」ということです。
気象病や自律神経の不調を診察するのに骨格のゆがみに注目してはいますが、人間は他にもさまざまな側面を持っていますよね。身体・心・社会のバランスが整ってこそベストな状態でいられると思います。不調がさまざまであるように、食事や睡眠、運動、メンタル、人との繋がり、社会生活など、その人に必要なアプローチもさまざまです。気象病は気象変化による不調ですが、セルフケアで多方面から補っていくことで症状は改善に向かいますし、うまく付き合っていけるものです。
本書では、私の長年の臨床経験をもとに、気象病の正体・治療・対策まですべてをお伝えし
ています。
- どこから読んでも役立つ本
本書の構成は、前半が知識編、後半が実践編という構成です。
前半は気象病を知るための基本的な知識や、気象病と関係の深い自律神経についてご紹介しています。診察中のような質問形式になっているので、知りたい部分だけを選んで読むことができます。
後半は、生活の中でできる具体的なセルフケアや、骨格のメンテナンス方法(主に運動療法)についてです。気象病と深く関係している自律神経ですが、その自律神経を整えるための要となるのが、「骨格」です。
パーソナルトレーナーさんにもご協力頂き、より専門的で、他の本にはないセルフケアの内容が詰まっています。
- 初公開のセルフケアが充実しています
「気象病ハンドブック」の大きな注目ポイントの一つが、いつもお世話になっているトレーナーさんにセルフケア監修をして頂いたことです。何度も言っていますが、私が専門外来で行っている治療で特徴的なのは、パーソナルトレーナーとの協働治療です。
気象病は自律神経の脆弱さや乱れが大きく影響しています。自律神経を乱したり、不調の引き金となるのが骨格のゆがみです。たとえば、ストレートネックや反り腰、側弯などがありますが、これらのような骨格の歪みがあると首肩こり・頭痛・めまいなど不定愁訴が起きやすくなります。
私は、気象病や自律神経の患者さんの症状を診ていますが、ストレッチなどのセルフケア指導はできても、骨格そのものを治すことは難しいです。
そこで、筋肉・骨格・運動のプロであるパーソナルトレーナーさんの力をお借りして、気象病の方々の治療を行っています。(パーソナルトレーナーによる運動療法や骨格の調整の介入が無くても、投薬や簡単なセルフケアで良くなる患者さんも多くいらっしゃいます)
そのトレーナーさんに監修いただき、一緒に本を作ったことで、今まで公開してこなかった具体的なセルフケアが充実しています。個人的には、トレーナーさんのお名前もやっと公開できることがうれしいです。
気象病専門外来の医師として…
この本は私にとって、ターニングポイントとなる一作です。
昨今、気象病が注目され始めていますが、気象病に関する知識とセルフケアがここまで具体的に書かれているものはまだ無いのではないかと思っています。
また、医師とパーソナルトレーナーが協働して製作できるのは、現段階の日本ではとても珍しいことです。医療と健康、両者の専門家によるセルフケアなので、気象病に苦しむ方、不調なのに気象病であることにまだ気づいていない方など、さまざまな方のお役に立ってほしいと願っています。
Blogメニュー
▶Blogトップ