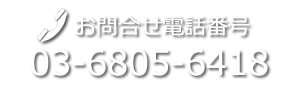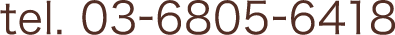ビタミンD欠乏について
2026年2月15日 15:56更新
専門外来コラム
最近こんな症状はありませんか?
・なんとなくずっとだるい、倦怠感が続く
・やる気が出ない
・気分が落ち込みやすい
・頭が重い、頭痛が増えた
・立ちくらみがある
・朝なかなか起きられない
・筋肉が重い感じがする
・風邪をひきやすい
「疲れているだけなのかな」
「気のせいかも」
「メンタルが弱っているのかな」
でも、その不調の背景に
ビタミンDは単なる「骨のビタミン」ではありません。
主な働きは、
・カルシウム吸収を助け、骨を強くする
・免疫を整える
・筋肉の働きを支える
・神経の炎症やホルモン調整に関与する
・自律神経や血圧調整にも関わる
特に重要なのが、
日光(紫外線)を浴びることで体内で作られるという点です。
つまり、日照時間が短い冬や、外出が少ない生活では不足しやすいのです。
冬に増える理由:
寒冷地や冬場では、
・日照時間が短い
・外に出ない
・厚着で肌が露出しない
・在宅時間が増える
これらが重なり、ビタミンDが十分に作られません。
① 倦怠感・だるさ(気象病・天気病外来、寒暖差疲労外来、自律神経失調症外来でも、1か2番目に多い症状です)
最も多いのが「なんとなく続くだるさ」です。風邪ではないのに、数週間続く疲労感。
階段がつらい、体が重い。でも熱はない。
これらが特徴です。
② 気分低下・やる気の低下
ビタミンDはセロトニン調整に関与します。
不足すると
・気分が沈みやすい
・やる気が出ない
・ぼーっとする
といった状態になりやすいのです。
冬季うつ(冬季気分障害)との関連も指摘されています。
③ 頭痛
意外に知られていませんが、ビタミンD不足と頭痛の関連も報告されています。
・慢性的な鈍い頭痛
・締め付けられる感じ
・片頭痛の頻度増加
ビタミンDは神経炎症や血管反応の調整にも関わっているため、不足すると頭痛が起こりやすくなると考えられています。月に5回以上頭痛がある場合は、「もしかしたらビタミンDが足りてない」?と思ってみても良いでしょう。
④ 低血圧・立ちくらみ
あまり注目されませんが、ビタミンDは血管や自律神経の調整にも関与しています。
不足すると
・朝起きられない
・立ちくらみがする
・ふらっとする
・脈が弱く感じる
・血圧がいつもより低い
といった症状が出ることがあります。(自律神経失調症との鑑別が難しい、もしくは自律神経失調症の場合に低血圧があることも多い。)
特に若い女性はもともと低血圧傾向の方が多いです。(低血圧でも無症状なら、特に問題はないです。)
冬場にさらに悪化して
「やる気が出ない」
「動き出せない」
しかしそれは怠けではなく、
体の循環が落ちているサインかもしれません。
⑤ 筋肉・骨の違和感
・太ももやふくらはぎの重さ
・背中や腰の鈍痛
・押すと痛い部位がある
重度になると骨軟化症へ進行することもあります。
⑥ 免疫低下
・風邪をひきやすい
・治りが遅い
免疫細胞にもビタミンD受容体が存在するため、
不足は感染リスク上昇と関連します。
⸻
「怠け」ではない
重要なのはここです。
ビタミンD不足や低血圧による不調は、
気合いではどうにもなりません。
「甘えている」
「根性が足りない」
ではなく、
生理的に起きている変化なのです。
どう判断するのか?
血液検査で「25(OH)ビタミンD3濃度」を測定します。
30ng/mL以上:理想値は40~80ng/mL
20〜30:不足傾向
20未満:欠乏
また、血圧も参考になります。
・収縮期血圧が90㎜Hg前後
・立ち上がるとふらつく
こういった場合は、循環状態も合わせて確認するとよいでしょう。
対策
・日光を10〜20分浴びる(顔と手)
・サプリメント(一般的に1000〜2000IU/日)
・サーモン、卵、干し椎茸などの摂取
・朝は急に立ち上がらず、ゆっくり体を起こす
・水分をしっかり摂る
※高用量摂取は医師の指示のもとで。
最後に
もしあなたや大切な家族が
・数週間続くだるさ
・頭痛
・気分の落ち込み
・立ちくらみや低血圧
・原因不明の不調
を感じているなら、ビタミンDという選択肢を思い出してください。
冬の不調は、心の弱さではありません。体からの静かなサインかもしれません。
「自律神経 これ1冊ですべて整える」が発売されます
2025年10月29日 07:53更新
専門外来コラム
10月コラム
「自律神経 これ1冊ですべて整える」東洋経済社 から発売されます。
「朝、何となくだるい」、「ベッドから起きるのがつらい」、「体が動かない」、「頭痛が治療をしても改善しない」、「めまいが改善しない」、「胃の不調が改善しない」など受診される方からお聞きすることが多いです。
頭痛は脳神経外科か脳神経内科で頭部MRIや診察で目立った異常はないとのこと。
めまいは耳鼻科で聴力検査やめまい検査で目立った異常はないとのこと。
動悸は循環器内科で心電図、レントゲン、心エコー、ホルター心電図、採血で目立った異常はないとのこと。更年期障害を疑い、婦人科で診察や検査を受けても、特には問題なしとのこと。
胃の不調があり、消化器内科で腹部エコー検査や、胃カメラを受けたが、特には問題ないとのこと。
原因がはっきりしないのはつらいですよね。
患者さんはつらい症状なので、生活習慣を変える、睡眠時間を確保する、食事をしっかりとる、ストレスをためない、運動をする、服薬をしっかり続けるなど様々な方法で対策をしています。
しかし、改善せずに悩まれている方で、当院の「頭痛外来」「首肩こり外来」「自律神経失調症外来」「気象病・天気病外来」「寒暖差疲労外来」を受診される場合が多いです。
この専門外来の中で、単独の外来を受診される場合以外に、頭痛外来と気象病外来、自律神経失調症外来と気象病外来というように、2つ以上を希望される方が結構おられます。
そのような場合に、診察をする際に大事にしていることがいくつかあります。
- まずは、1番目、2番目、3番目につらい症状を聞いています。いつからですか?
- 専門的な問診表+で必要と思われる項目を質問します。
- 診察をしていきます。一般的な内科的診察です。そして、神経内科専門医としての診察を行います。
- 専門的(当院での専門外来的)な診察を行います。
これらを判断して、どのような治療が適しているのかを決定しています。
そして、該当する患者さんの場合には、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲが関係しているのかを評価するようにしています。
Ⅰ:自律神経
どんな状態なのか(頭痛、首肩こり、めまい、動悸、だるい、倦怠感、立ちくらみ、午前中調子が悪い、寝付けない、長時間眠れない、気分が落ち込む、気分がアップダウンする、イライラする)を、話を聞くことが大事です。
「自律神経失調症じゃないかと思って」、「自律神経が原因だと思う」と話される方も多いです。
→ただ私からは、なるべく自律神経の話はしないようにしています。
自律神経が原因とされる場合は、心身の不調の割合を把握することが重要だからです。
「不調の割合」というキーワードを使用することが多いです。
- 心の不調が大きいのか、②身の部分が大きいのか、③心身が混在している。
この3つをなんとなく把握しようとしています。
Ⅱ:骨格(姿勢)
そして、診察開始に行うようにしているのが、姿勢、歩き方、座り方、頭の位置などをチェックします。このチェックで、頭痛の左右差、首肩こりの左右差があるのか、腰痛の左右差が把握しやすくなります。だるい、全身倦怠感を訴える場合にも、診断のポイントになる場合があります。
Ⅲ:気象
天気に影響を受けるのか?を問診でチェックするようにしています。
- 天候が悪い時に体調が悪い
- 雨が降る前や天候が悪化する前に、何となく天気の予測ができる
の2つの質問です。気圧、気温、湿度です。
このⅠ・Ⅱ・Ⅲのどちらが該当するのか。そして、3つの割合を比較するようにしています。
当院の専門外来は、頭痛外来→首肩こり外来(Ⅱに該当)→自律神経失調症外来(Ⅰに該当)→気象病外来・天気病外来(Ⅲに該当)→寒暖差疲労外来(Ⅲに該当)という順番になっています。
脳神経内科専門であったことから、頭痛を診察することが多く、頭痛(緊張型頭痛、片頭痛)には首肩こりが関係していました。
2013年の開業当時から、頭痛外来と首肩こり外来は、専門外来として立ち上げていました。
そして、自律神経失調症といわれる症状には、首肩こりが関係しているというホームページの内容をみて、受診される方が多くなりました。自律神経失調症で臨床的に説明できる方にも、首肩こり外来での同じような診断方法と治療(セルフケア、生活習慣、投薬)で
結果が出ました。
自律神経失調症を、心身の症状に当てはめていくことが重要であると実感して、自律神経失調症外来を立ち上げることになりました。私自身が、自律神経失調症を、検査をしても原因がわからない不定愁訴と捉えていた時期があっただけに、パズルが解けるような感触を得ていました。
しかし、頭痛やめまいを訴える方には、曇りや雨、台風、ゲリラ豪雨などで、症状が悪化する方が多かったです。
天気関係だよね、調子が悪くなるのは、当たり前だよねと考えていました(ただ診察をしていても自分自身で納得できていない部分がありました)。
天気の不調でも、特に気圧の変化で不調になる場合が多くみられていました。
開業から3年が経過して、不調の原因に天気が関係していることが多いという臨床経験が積み重なっていきました。
専門外来の必要性を強く感じて、
2016年9月に気象病・天気病外来を専門外来として立ち上げることになりました。
2017年5.6.7月の梅雨前後の時期には気象病(気圧差)の治療でそれなりの結果が出るようになりました。
しかし、夏場にエアコンで冷えて不調、外が暑くて不調の方が見られるようになりました。温度差による不調が原因でした。
2017年7月頃に、「冷房病・クーラー病外来」を立ち上げました。クーラーを使う夏場の不調が目立っていました。しかし、春(寒い時から暖かくなる時)と秋(暖かい時から寒くなる時)にも同様の症状がみられていました。温度差による体調不良が年間で起きていることが理解出来ました。
そして、2018年7月頃に「寒暖差疲労外来」へと名前を変えることになりました。
あっちこっちしていると思われるかもしれませんが、患者さんの不調をたどっていくと、今の診察方法が適しているなと感じています。
そして、「自律神経」、「骨格(姿勢)」、「気象(気圧・温度・湿度)」という3つを、相互的にとらえていくことが大事だと考えております。
この3つを診察と治療に組み合わせていくことで、それなりの結果が出るようになりました。まだまだ勉強、研鑽、考察、研究ともになりないと自覚はしています。
いままで、いくつもの出版社の方々からお力を貸していただけたことで、「自律神経の書籍」、「気象病の書籍」、「背骨(骨格)の書籍」を出版することが出来ました。
2025年10月29水曜日に、東洋経済社さんから、新刊を発売させていただけることになりました。
自律神経、気象(気圧・湿度・気温)、骨格(姿勢)を3本柱とした、内容となっています。
今までの診療方針をまとめた感じのないように仕上げることが出来ました。患者さん、スタッフ、そのほか様々な方に支えられて、発売することが出来ました。ありがとうございます。
「自律神経 これ1冊ですべて整える」
www.amazon.co.jp/dp/4492048189
です。
出来るだけ、より多くの有益な情報をお伝えすることが出来たらと考えております。
2025・9 気象病が女性に多い理由は?―自律神経や女性ホルモンとの関係―
2025年9月3日 06:44更新
専門外来コラム
2025・9
気象病が女性に多い理由は?―自律神経や女性ホルモンとの関係―
9月になり、台風や秋雨前線の影響で再び気象病が気になる季節になりました。気象病とは、気象変化によってさまざまな体調不良が起こることを言います。気象病の症状を訴える人は女性が多いですが、当院を受診される患者さんの中では、女性は7~8割を占めています。気象病が女性に多いのは、女性ならではのさまざまな特徴が関係しています。たとえば、女性ホルモン、貧血、低血圧、筋肉量・骨格、冷え性・むくみなどです。また、特にホルモンや筋骨格の要素は自律神経の乱れにも大きく関わっており、自律神経が乱れていると気象病も起こりやすくなります。
- 気象病と自律神経の深い関係
気象病と自律神経は密接な関係にあります。気圧低下や寒暖差などの気象変化が起きると、それに体を適応させるために自律神経が反応して乱れるためです。たとえば、気圧が下がった時、内耳にあるセンサーが気圧の低下を感じ取り、その情報が自律神経の中枢に届きます。気圧低下という変化に対して微調整を行うために交感神経・副交感神経のバランスが乱れ、不調につながります。そのため、気象病の症状と自律神経の不調の症状は似通っているところがあります。そして、自律神経が乱れている人は気象病になりやすいです。
- なぜ気象病は女性に多いのか?
[女性ホルモンの影響]
女性には月経周期ごとにホルモンバランスの大きな変動があります。女性ホルモンにはエストロゲンとプロゲステロンの2種があり、自律神経にも影響を及ぼします。特に排卵後から生理前はプロゲステロンが増えて、副交感神経が優位になりやすく、だるさや眠さなどが出やすくなります。一方で、ホルモン低下期には不安・イライラなどの心の不調が出やすくなります。このように、生理周期や更年期などでホルモンバランスが乱れると、自律神経も乱れやすくなります。自律神経は気象変化にも敏感であるため、自律神経が乱れていると、気象病の症状がより出やすくなります。
[筋肉量が少なく冷えやすい]
女性は筋肉量が少ないため、体の熱を産生する量が少ないです。そして血流が悪くなりやすいため女性は体が冷えやすく、自律神経の乱れを助長します。冷えると特に交感神経の緊張を招き、血行不良、頭痛、肩こり、不眠などの症状が出やすいです。また、寒暖差疲労になると、体が感じる大きな温度差に体温調整が追いつかず、冷えの症状が出る場合が多くあります。その影響で気温や湿度の変化で冷えが悪化し、不調の悪循環に陥りやすいです。
[片頭痛の有病率が高い]
片頭痛はもともと女性に多く、数でいうと男性の約3倍と言われています。片頭痛は気圧や天気の変化に影響を受けるため、天候が悪くなったり季節の変わり目になったりすると片頭痛が悪化しやすいです。気象病で最も訴えが多い症状が頭痛ですので、気圧の変化などで頭痛は起こりやすく、気象病に女性が多い一因ともなっています。
[ライフイベントによるストレスや変化が多い]
妊娠・出産、育児、更年期など、女性はライフイベントによって生活スタイルやホルモンの変化が大きいです。これに伴い、心身のバランスも崩れやすく、自律神経が安定しにくい傾向があります。自律神経が苦手としているのが「変化」です。そのため、様々な変化が重なると自律神経が乱れ、気象病が発症しやすい状況ができあがります。
- 女性特有の気象病症状
[月経痛・PMS(月経前症候群)・更年期症状の悪化]
女性ホルモンと自律神経には深い関係があるため、女性のホルモンバランスに大きな変化が訪れる月経前後や更年期に気象変化が重なると、症状が重くなることがあります。実際、PMSの症状を持つ女性の3人に1人が天候の変化で症状が酷くなると言われており、頭痛、倦怠感、腹痛・気分の落ち込み・イライラ・不眠などのPMS症状が天気の変化と連動して強くなることがあります。そして更年期の女性は、ホルモンの急激な変化で自律神経が乱れやすく、その状態で気象の影響を受けるとのぼせ・ほてり・めまい・倦怠感などが悪化しやいです。
[冷え性やむくみ]
女性は元々冷えやすい体質にありますが、低気圧が訪れると体に水分を溜めこみやすくなるため、血行が悪化し、冷えやすくなります。低気圧の状態は、飛行機に乗るのと似たような状況です。飛行機でポテトチップスの袋が膨らむ現象があるように、私たちの体も大気圧が変化することによって膨らみ、むくみとして現れます。
[メンタルの不調(気分の落ち込み、涙もろさなど)]
気象病による自律神経の乱れで、うつや不安感、情緒不安定などメンタル面での不調が起こることがあります。特に雨の日や曇天が続くと、幸せホルモンと呼ばれるセロトニンの分泌が減りやすいため、精神的に沈みやすい状況です。気圧が下がるのと同時に、不可抗力で気持ちの急降下が起こる人も少なくありません。「気圧のせい」だと自覚ができると少しは気持ちが楽になるでしょう。
- 女性の心と身体のバランスを整える運動
[ヨガ・ピラティス・背骨リセット]
背骨は自律神経の通り道であり、背骨を意識して動かすこの3つの運動は自律神経を整える効果があります。ゆっくりとした深い呼吸をすることで、ストレスを軽減したり、不安の解消、睡眠の質の向上などが期待できます。また、血流が良くなるため、PMSや月経痛の緩和にも役に立つでしょう。ピラティスや背骨リセットは体幹の筋力を強化する効果もあり、筋肉量が少なく冷えやすい女性の健康全般の健康面のサポートになります。
[ウォーキング(特に朝の散歩)]
ウォーキングは無理なく手軽に続けやすい運動の代表例です。外に出て太陽光を浴びるとセロトニンが分泌され、うつ傾向を予防し気分が向上します。有酸素運動は「心の鎮静剤」ともいわれており、メンタル面の底上げになるでしょう。
[ダンス・エクササイズ(ズンバ・バレエなど)]
音楽と一緒に体を動かすことで、ドーパミンやエンドルフィンといった快感系のホルモンが分泌されるため、気分転換・ストレス解消にぴったりの運動です。自分を表現することが自信や解放感にもつながります。
自律神経に優しい環境づくりと夏でもできるセルフケアー
2025年8月7日 06:51更新
専門外来コラム
夏に気をつけたい自律神経の不調は?―自律神経に優しい環境づくりと夏でもできるセルフケアー
梅雨が明け、台風が通過しない限りは、気象病を気にせずに過ごせる期間に入りました。梅雨明け後は夏を楽しみたいところですが、最近の夏は35℃以上の高温、熱帯夜、湿度も高く、うだるような蒸し暑さが長期間続くようになりました。危険な暑さや熱中症警戒アラートのために外出を控える人も珍しくなくなり、室内で過ごす時間が増えていると思います。その結果、熱中症以外にも夏に起こりやすい不調や対策も変わってきており、私たちも日々アップデートしなければいけません。夏の過ごし方は秋の体調にも影響しますので、夏の体のメンテナンス法を身に付けましょう。
- 夏に気をつけたい自律神経の不調
[冷房病]
冷房病とは、冷房の効いた環境に長時間いることによってさまざまな不調が出ることを言います。正式な病名ではありませんが、夏の代表的な不調の一つです。冷房病で起こる不調は、自律神経や冷えによる血行不良が関係しています。症状は、冷え・むくみ、首肩こり、倦怠感、胃腸の冷え(食欲不振、腹痛、下痢など)、女性の場合は月経に影響が出ることもあります。最近では熱帯夜が続いているので夜間も冷房を付けっぱなしにする方が大半だと思いますが、冷房病の影響で朝から体がぐったりしていることもよく聞くお話です。
[夏の寒暖差疲労]
寒暖差疲労といえは春や秋のイメージですが、夏は室内外の気温差の影響が大きいです。寒暖差疲労というのは、私たちの体温調節を担当している自律神経が急激な温度差にうまく対応しきれず、疲労感、冷え、首肩こり、頭痛などさまざまな不調が起こることを言います。夏の場合は、冷房の効いた室内環境と35℃を超える外気を行き来すると、大きな温度差を体験することになります。すると、体温調節がうまくいかなくなり、自律神経が乱れて不調につながります。疲労感、倦怠感、頭痛、めまい、食欲不振、不眠、冷えやのぼせ、肌トラブルなどが主な症状です。自律神経の乱れ、血行不良が関係しているという点では冷房病と似ています。
[不眠]
近年の夏は熱帯夜が当たり前になっており、蒸し暑さによる不眠が起こりやすいです。私たちは眠っている間、大量の汗をかきます。夏は気温が高いだけでなく湿度も高いため、汗が蒸発しにくく、不快感や体温調節の不良が影響して睡眠の質を下げてしまいます。また、夏は活動的なイメージがあるかもしれませんが、1日中冷房の効いた部屋で過ごし、運動不足になる季節へと変化してきました。そのため、日中の活動不足で眠りづらくなっている現状もあるでしょう。
- 湿度が与える自律神経への影響は意外と大きい
[湿度と自律神経]
自律神経には体温調節を行う役割がありますが、湿度が高いとその機能が乱れやすく、交感神経が過剰に優位な状態になります。また、湿度が高いことで汗が蒸発しにくく、体温がうまく下がらないため、体に熱がこもります。すると、熱中症のような症状、頭痛、吐き気、ほてり、だるさなどが出やすいです。
[湿度と体感温度]
みなさんは湿度と体感温度の関係をご存じでしょうか。私たちの体は、湿度が高いと暑く感じ、湿度が低いと涼しく感じます。湿度が高いと汗が蒸発しにくくなるため、体が熱をうまく逃がすことができず、暑さを感じやすくなります。特に、湿度が70%以上になると体感温度が急激に上昇し、実際の気温より5℃以上も高く感じることもあります。反対に、湿度が低いと汗が蒸発しやすくなるため、体温が効率よく下がります。
・気温25℃ / 湿度60% → 体感温度は約27℃~28℃程度
・気温30℃ / 湿度80% → 体感温度は35℃以上に感じることも
・気温25℃ / 湿度40% → 体感温度は23℃~24℃程度に感じやすい
このように、湿度が高いと、私たちの体は気温以上に暑さを感じます。そのため、湿度をコントロールすることが快適な生活には不可欠です。
- 自律神経に優しい夏の過ごし方
[冷房病の対策]
冷房病対策のポイントは自律神経の乱れを防ぎ、冷えによる血行不良を避けることです。室温を26~28℃に設定し、強く冷やし過ぎないこと、そして直接風に当たらないことをお勧めします。冷え対策のグッズとしては、ひざ掛け、上着、ストール、レッグウォーマー、靴下(足首が隠れることが大切です)を活用すると良いでしょう。首・足首・手首、お腹には大きな血管が流れているため、この4点を守るようにすると冷えすぎるのを予防できます。また、飲みものはなるべく温かいものを飲み、夜は入浴で体の内側から温めると良いでしょう。
[寒暖差疲労の対策]
まずは寒暖差が起きにくい環境調整をしましょう。急な温度差が発生しないように、冷房の温度設定を低くし過ぎず、そして扇風機などの風を使って空気の流れを作ると良いと思います。寒暖差疲労に対してできることは、服装でも体温調節ができるように工夫すること、入浴で冷えのリセット、こまめな水分・ミネラル補給、睡眠の質の確保、軽い運動やストレッチ、深呼吸でリラックスなどです。
[湿度を考慮した環境調整]
適切な湿度調整をするだけでも、暑さによる不快感や自律神経の不調が起きにくくなります。まずはエアコンの除湿機能を使用して体感温度を下げる工夫をしてみましょう。夏は湿度50%を目安に、ご自身が快適と思える湿度を探してみてください。さらに、風通しが良いと湿度がこもりにくくなり、涼しさを感じることができます。サーキュレーターや扇風機を活用して空気の流れを作りましょう。また、夜は除湿器を活用しながら、通気性の良いシーツや寝具・冷感マットなども併せて使用することで、「涼しいけれど体が冷えない」と思う環境を探せると、不眠の解消につながると思います。
- 夏でも続けたい背骨の運動
夏は自律神経が乱れやすく、運動不足にも陥りやすいため、心身のメンテナンスが難しい季節になってきています。疲労の溜まる日々だからこそ、自分自身のメンテナンスは欠かしてはいけません。そこで、室内でもできる運動をご紹介します。
[ヨガ]
ヨガは呼吸法とストレッチを組み合わせた運動で、自律神経の調整に効果があります。初心者でも手軽に始めやすく、室内で行えるため、無理なく継続できます。ヨガのポイントは呼吸です。呼吸に集中することで、副交感神経が優位になり、リラックスすることができます。
[ピラティス]
ヨガと似ているようで異なるのがピラティスです。ピラティスは体幹を鍛える運動が多く、呼吸と筋肉を意識的に使うため、自律神経のバランスを整えるのに効果があります。背骨リセットの効果もあり、私は患者さんにもピラティスをお勧めしています。特に、背骨を意識して姿勢を正すことが多いため、日常生活の中での体の使い方にも良い影響を与えます。
[背骨リセット]
背骨は自律神経などの大切な神経の通り道です。背骨が歪んでいると自律神経が乱れる原因になり、夏の暑さにも耐えられなくなってしまいます。背骨のリセットは、体の中心軸を整え、姿勢の改善、筋肉の緊張緩和、体幹の強化、血行促進、内臓の調整、自律神経機能の活性化など、さまざまな効果があります。日々継続していくことで不調の起こりにくい体の土台を作ることができます。
気象病治療に効果のある五苓散の使い方
2025年7月4日 07:27更新
専門外来コラム
気象病治療に効果のある五苓散の使い方
日本の異常気象が進むにつれて、気圧や気温の大きな変化で体調を崩される方が増えました。気象病専門外来を始めて約9年経ちますが、年々、気象病の認知度が高まっていると感じています。気象病の治療薬として数年前から注目されているのが、五苓散という漢方薬です。昨年、学会誌で「気象変化に伴う頭痛に対する五苓散の有効性と安全性」という題目で論文を発表させて頂きました。気象変化によって体調不良を訴える患者さんが増加しているという現状もあり、気象病の治療や五苓散などに関心を持つ医師も多く、気象病治療の需要の高さを実感しています。
205/6/7には、日本東洋医学会総会にて、ランチョンセミナーで発表をさせて頂きました。800名以上の現地での参加者があり、気象病への認識の高さが強いと再認識しました。
今回のコラムでは、東洋医学における気象病の捉え方や五苓散についてご紹介していきます。
- 気象病は水滞によって起こる
東洋医学において、健康とは「気」、「血」、「水」のバランスが整っている状態と捉えます。そして、気と血と水のバランスが崩れたとき、不調が出ると考えます。気象病は、「水滞」といって「水」のバランスが崩れており、水の巡りが滞った状態です。「水」は血以外の体液のことを指し、組織液やリンパ液がそれに当たります。気圧の変化が起こると、体内で水の流れや水の状態に異常をきたし、気象病に特徴的な頭痛やめまい、倦怠感といった症状が出やすくなります。
- 「水」のバランスチェックをしてみましょう
「水」のバランスを見るために、以下の項目に当てはまるかどうかチェックしてみましょう。多く当てはまる方ほど体が水滞に偏った状態と言え、気象病の症状も出やすいです。
・浮腫みになりやすい
・天気が悪いと体調が優れない
・雨が降る前など、天気が変わることを予測できる
・めまいや耳鳴りが起こりやすい
・軟便・下痢ぎみ
・頭が重い
・体が重い
・車酔いしやすい
- 気象病の薬物治療は五苓散からスタート
[五苓散の効能]
五苓散という漢方は、体内の水分バランスを改善する代表的な利水薬です。副作用が少なく、飲みやすいのも特徴です。五苓散は、ソウジュツ、ブクリョウ、チョレイ、タクシャ、ケイヒという5つの生薬が配合された漢方です。五苓散には、体のむくみが取れて気象病の症状を和らげるはたらきがあります。気象病に限らず、頭痛やめまい、むくみ、二日酔いなどの改善にも広く用いられます。
[気象病での使い方]
気象病の方にまず私がお勧めする五苓散の飲み方は、定期投与です。定期投与というのは、1日2~3回、決まった時間に、一定期間飲み続けることを言います。飲み始めは体に溜まった余分な水分が排出されるので、尿がいつも以上に出たり、頻尿になったりすることがありますが、徐々に落ち着いてきます。一旦、水分バランスを整え、症状のコントロールがついてきたら、症状が出た時や気圧変化が大きい時だけ頓服で飲む方法にするのも良いでしょう。
- 論文「気象変化に伴う頭痛に対する五苓散の有用性と安全性」
先日、頭痛学会で五苓散に関する論文の発表をさせて頂きました。少しだけ内容をご紹介します。気象変化(気圧・寒暖差・湿度)に伴う頭痛に対する五苓散の有効性と安全性を目的とし、①気象病があり、気象変化に伴う頭痛がある②初診以降も来院している、これら2つの条件を満たしている患者さんを対象としています。
五苓散の投与方法は、7.5mgを1日2~3回、食前または食間に経口投与としました(患者さんの年齢や体重、症状により量は適宜増減)。その結果、1週間あたりの頭痛の回数、頭痛の程度、鎮痛薬の使用回数、すべてにおいて有意な減少が認められました。特に、痛みの程度に関してはほぼ半減したというデータが出ております。この研究から、五苓散は、気象病で頭痛を訴える患者さんにとって症状をやわらげ、QOLを上げるのに役立つ漢方薬であるということが明らかになりました。
- 漢方以外で水の巡りを改善する方法
五苓散で水滞が改善する方でも、可能であればお薬は最小限にしたいですよね。普段の生活で水の巡りを良くする習慣も大切にしていきましょう。
[運動]
運動は、血の巡りが良くなり老廃物が溜まりにくくなるため、体の余分な水分も溜まりにくくなります。特に、ウォーキングやジョギング、水泳などの有酸素運動は、全身の巡りが良くなり、むくみの予防・改善につながります。余分な水分は、重力に従って身体の下の方に溜まりやすいです。1日の終わりにふくらはぎをマッサージすると、疲労物質が血管に運ばれてむくみが改善されます。また、普段からストレッチの習慣や背骨を動かす運動(ヨガやピラティスなど)を継続していると、血行不良が起きにくい体になります。
[入浴]
入浴には、全身を温めて血流を改善する効果がありますが、静水圧作用といって、湯船の水圧が全身に加わることで血行を促進し、むくみを解消する効果もあります。身体に余分な水分が溜まっているということは、身体が冷えやすくなるということです。血流が悪くなり、身体に老廃物が溜まるため、入浴で日々の冷えをリセットすると良いでしょう。入浴は水の巡りに限らず、睡眠の質を上げたり、自律神経を整えたりと、さまざまな健康効果があります。
2025・6 気象病による頭痛の特徴とその対策
2025年6月10日 21:39更新
専門外来コラム
2025・6 気象病による頭痛の特徴とその対策
気温とともに湿度も上がり、梅雨の蒸し暑さを感じる日が増えてきました。5月から7月にかけての時期は、気象病の患者さんが増えていきます。気象病というのは、気圧や気温、湿度の変化により引き起こされる心身の不調のことです。正式な病名ではありませんが、「気象病」はここ数年でかなり身近な言葉になってきていると感じています。気象病は気のせいという訳でも、心の病気でもありません。しかし、検査で明らかな原因がわからないため、周囲の人からは理解されづらく、悩まれている方も多いでしょう。気象病は女性に多く、頭痛を訴える方が圧倒的に多いです。今回は、気象病による頭痛の特徴と対策についてご紹介します。
- 初夏から梅雨は気象病患者が最も多いシーズン
5月から7月の時期は、春から夏への移行時期、そして梅雨が始まります。最近は涼しくなったり暑くなったりと、気温の変化が激しいですよね。気圧の上下・気温の上昇・湿度の上昇が重なると、自律神経に負担がかかり体調を崩しやすくなります。この時期は、気温が上昇していくと同時に湿度も上がります。湿度が体感温度に与える影響は大きく、早い段階から想像以上の蒸し暑さを感じるようになります。
自律神経は私たちの体の体温調節を行っていますが、蒸し暑さにより汗が蒸発しづらい状況が続くと、熱がこもって頭痛や気分不快などの症状が出やすくなります。体温調整するために、すでに自律神経に負担がかかっている中、さらに気圧の上下がプラスされると、その負荷に耐えられず症状が出たり強く出たりします。
- 気象病で起こる2種類の頭痛
気象病の症状は様々ですが、8割以上の人が頭痛を訴えます。気象病で起こる頭痛は命には関わりません(一次性頭痛に分類されます)が、痛みによって生活に支障が出るため、辛い症状です。気圧の上下で頭痛が出る人、気圧の上下をきっかけに片頭痛の発作が起こる、緊張性頭痛が悪化する人などがいます。
[片頭痛]
片頭痛は、頭の片端もしくは両端がズキズキと強く痛むのが特徴です。緊張から解放されたとき、寒暖差、気圧変動など、なんらかの刺激によって脳の血管が拡張し、それが神経を刺激して痛みとして発生します。特に片頭痛が起こりやすいのは気温が急上昇したときと、気圧が下がった時です。気温の上昇、気圧の低下とともに副交感神経が優位に働き、血管が拡張して片頭痛が起こりやすくなります。寒暖差と気圧の上下が重なる季節は、常に頭痛に悩まされるという方もいます。
[緊張性頭痛]
緊張性頭痛は、全体的に頭を締め付けられているような鈍い痛みが出るのが特徴です。片頭痛とは異なり、左右差はありません。緊張性頭痛が起きるのは、気温が下がって身体が緊張した時や、気圧の変化でストレスを感じて交感神経が優位になった時です。身体が緊張したり交感神経が優位になると、首・肩の筋肉も収縮して首肩こりを引き起こし、それが頭に派生して頭痛になります。緊張性頭痛に悩まされている人は多く、患者さんからのニーズは高くありますが、片頭痛ほどは注目されていないため、薬の選択肢が増えないのも特徴です。
- 頭痛が起きた時の応急処置
[片頭痛]
片頭痛が起きた時は、とにかく刺激の少ない環境で横になって休むことをお勧めします。動いたり、お風呂などの血流が良くなることをしたりすると、ズキズキとした痛みの元になりますのでご注意ください。頭頂部やこめかみなどを氷枕で冷やすと症状が和らぐことがあります。首まで冷やしてしまうと全身が冷えて緊張してしまいますので気をつけましょう。
[緊張性頭痛]
緊張性頭痛の締め付けられているような痛みは、筋肉の過緊張によるものです。そのため、血行を良くしたり、心身の緊張を緩めたりすると頭痛を和らげることができます。首肩こりが関係していることが多いので、お風呂に首まで浸かり、ストレッチをしてみましょう。片頭痛は温めると悪化しますが、緊張性頭痛の場合は、温めて筋肉をほぐした方が効果があります。頭痛によって対処法が異なるためお気を付けください。
- 気象病は女性に多い
気象病に悩む方は、圧倒的に女性が多いです。実は気象病は、女性ホルモンと関係しています。月経周期や更年期などのホルモンの変化に伴い、気象関連の負荷がプラスされると、不調が起こりやすくなります。たとえば、生理前に片頭痛の症状が出やすい方は、気象病でも頭痛が頻発することがあります。女性ホルモンであるエストロゲンやプロゲステロンが分泌されるには、脳にある視床下部という部分が関与しています。視床下部は自律神経の中枢でもあるため、気象病と女性ホルモン、自律神経は互いに切っても切れない関係なのです。不調の症状の種類も似ています。
- 頭痛の予防と改善のポイントは「首肩こり」
頭痛もち、気象病の方に共通しているのは、酷い首肩こりです。頭痛薬で痛みのコントロールをするのも1つの方法ですが、薬だけに頼らず、首肩こり対策をすることも重要です。私の外来では、セルフケアなどにより首肩こりが軽くなった患者さんは、薬の量も減っていきます。中には薬が全く要らないまでに頭痛が改善する方もいます。それほど首肩こりのセルフケアには意味があります。首肩こりが起こりやすい生活習慣の改善、ストレッチや背骨を動かす運動など、できることから実践してみてください。
首肩こりと不定愁訴-運動と漢方によるアプローチ②-
2025年5月8日 21:06更新
専門外来コラム
首肩こりと不定愁訴-運動と漢方によるアプローチ②-
前回のコラムでは、首肩こりの正体、そして首肩こりを引き起こす原因や生活習慣についてご紹介しました。では、自律神経失調症外来にいらっしゃる患者さんが首肩こりを解消すると、不調も一緒に改善していくのはなぜでしょうか?背骨や骨格のゆがみ、首肩こり(筋肉)、自律神経は、一見それぞれが独立した存在のように思われますが、実は関係し合っています。ストレートネックや猫背、反り腰など、程度の大小を考えなければ、骨格が乱れていない人はいません。特に首肩こりは日頃のセルフメンテナンスが結果として出やすい症状です。まずは自分の姿勢や骨格を知ることから始めてみましょう。
- 背骨は自律神経の通り道
背骨は、臼のような形をした小さな骨が連なって1本の背骨が構成されており、頚椎(首)・胸椎(胸)・腰椎(腰)・仙椎(お尻)と、部分によって名前がついています。特に、首には重要な神経がたくさん走っており、その中に自律神経も入っています。自律神経が通っているのは、背骨の中にある脊髄という場所です。交感神経は、胸髄(胸椎の部分)や腰髄(腰椎の部分)から出て背骨に沿うように走っており、副交感神経は、脳から首、腰のあたりから出ています。
背骨が歪んでいると、それだけ自律神経の通り道が妨げられてしまいます。背骨のゆがみが自律神経の不調の引きがねとなる理由の一つはここにあります。
- 首肩こり自律神経の不調や気象病との関係
[首肩こりによる血行不良が自律神経の働きを妨げる]
首こりで首の筋肉の血流が悪くなっていると、首を通っている副交感神経、そしてその先にある脳に十分な酸素や栄養が届かなくなってしまいます。その結果、副交感神経の働きを妨げることになります。また、肩・首・背中はさまざまな筋肉がつながってできているので、自覚の有無に関わらず、首が凝っていれば肩も凝っているでしょう。そして、背中の筋肉が緊張すると、そこから出ている交感神経に過度な刺激を与えてしまうかもしれません。
私は、気象病の対策を提案するのに、耳のマッサージだけではなく首や肩のストレッチもお勧めしています。自律神経が乱れている方は、それだけ気象病に対する耐性も低く、症状が出やすいです。首肩こりがあると自律神経の働きが低下するため、気象病を予防するためにも首肩こりのケアが必要なのです。
[呼吸への悪影響]
自律神経を整えるのにまず基本となるのが呼吸です。というのは、呼吸を整えることで、自ら交感神経と副交感神経を自分で調整することができるからです。息を吐くと副交感神経優位、息を吸うと交感神経優位に傾きます。自律神経が乱れて不調が出ている方は、大半が浅い呼吸をしており、本来の正しい呼吸ができていません。その原因の一つが、呼吸をするための筋群が凝り固まって動きが悪くなっているという点です。特に注目したいのは胸鎖乳突筋と斜角筋です。胸鎖乳突筋は耳の後ろから鎖骨にかけてつながっており、斜角筋は首の真横にあります。両者は息を吸うときに使う筋肉の一つで、硬くなると呼吸が浅くなります。ストレートネックなどで首や頭が前に出ている姿勢が続くと、これらの筋肉が硬くなり、呼吸のしづらい状態が当たり前になってしまいます。
- 首肩こりと漢方
首肩こりに効果的な漢方薬があるのをご存じでしょうか?葛根湯には、体を温め、冷えなどによる血行不良を改善するという効能があります。葛根湯といえば風邪のひきはじめに飲む印象が強いかもしれませんが、実は首肩こりにも使うことのできるお薬です。葛根湯には、クズ(葛根)、タイソウ、マオウ、カンゾウ、ケイヒ、シャクヤク、ショウキョウという生薬が含まれています。これらの成分が、体をじわじわと温め、特に頭や首周辺の筋肉の緊張を緩めてくれます。
私の外来では、首肩こりや体調不良が酷い患者さんに、セルフメンテナンスと併用して葛根湯を処方することがあります。漢方ではありませんが、首肩こりの症状や体調の重症度によっては筋弛緩薬やビタミン剤などを試すこともあります。
- 根本から治すなら脊椎全体を整える
首肩こりは日頃のメンテンナンスで差が出やすい場所です。いくら首肩を一生懸命ストレッチやマッサージをしても改善しない場合は、骨格のゆがみに理由があるかもしれません。
骨格のゆがみで代表的なのがストレートネックや猫背です。ストレートネックは、本来ゆるいカーブを描いているはずの頚椎がカーブを失ってまっすぐになっており、横から見ると、まっすぐ立っていても頭が前に出た姿勢になります。猫背は肩が内巻きになり(肩甲骨は外側に開いたような位置になります)、胸まわりの筋肉が硬くなっていることが多いです。胸椎の動きも悪くなっています。
土台である骨格が歪んでいると、自分にとって楽な姿勢をしているつもりでも、それを支える筋肉には負担がかかり、筋肉が伸びきって硬くなってしまっている可能性があります。そのような状態になってしまうと、凝っている部分をストレッチしただけではすぐに筋肉は元の血行不良の状態に戻ってしまいます。首は背骨の一部で下までつながっているので、背骨全体を整えて筋肉・骨格のメンテナンスをすることで、首肩こりを根本から改善することができます。急に背骨のケアと言われても難しいかもしれないので、まず基本として、「背骨の上に頭がポンっと乗っている感覚」というのを意識できることが大切です。
- まずは自分の姿勢を知ることから
ストレートネックや猫背、反り腰など、なんとなくは自覚していても、自分の背骨のカーブや動きの具合(可動域)がどの程度なのかを知る機会は少ないのではないかと思います。自分に必要な運動やメンテナンスをするために、まずはセルフチェックで自分の骨格について知りましょう。
[正面から縦の軸・横の軸のチェック]
身体のバランスを見るために、縦の軸と横の軸を考えます。鏡を見る前に3回ほど深呼吸をして力を抜きましょう。力んで姿勢を正そうとしてしまうと、普段の姿勢ではなくなってしまい評価がずれてしまいます。縦の軸とは、正面から見て眉間・アゴ・鎖骨と鎖骨の間、へそ、かかとの間の点を結んだ時の一本線です。背骨のラインも一緒にイメージできると良いでしょう。そして、横の軸とは、両耳をつないだ時にできる一本線です。その他にも、肩、骨盤、膝、くるぶしの位置もチェックすると良いと思います。
[壁を使って立ち方のチェック]
かかと、お尻、肩甲骨、の3点を壁に付けるように立ちましょう。力は抜いてリラックスした状態が好ましいです。見るべきポイントは2つです。
ⅰ壁に頭が付くか
ⅱ壁と腰の間にどのくらいすき間ができるか
大きくこの2点に分けて姿勢をチェックしてみましょう。頭は、後頭部が自然に壁に触れるのが理想的です。壁から離れてしまう方は、反り腰、猫背のどちらかの影響で頭の位置が前にずれてしまっているなどが疑われます。壁と腰の間のすき間は、壁と腰の間に指1本分のすき間ができる状態が理想です。すき間がこぶし1個分くらい空いている方は反り腰、逆にすき間がほぼできない方は猫背が強い可能性があります。背骨はお尻のあたりから1つずつ積みあがってS字にカーブを描いています。そのため、反り腰や猫背があると、首がバランスを取るために本来のカーブを無くします。こうしてできあがるのがストレートネックです。ストレートネックの方は、首だけが悪いというケースは少なく、反り腰や骨盤後傾、猫背など首より下の部分が大元の問題となっていることが多いです。
[頚椎(首)・肩・胸椎・腰・股関節]
ここまで読んで背骨全体を整える必要があるとわかって頂いた方は、背骨を頚椎(首)・肩・胸椎・腰・股関節に分けてメンテナンスをしてみましょう。細かく分けて評価をしてみると、自分の弱い部分、たとえば「胸椎が硬い」、「股関節の動きに左右差がある」などと気づくことができ、エクササイズも効果的に行うことができます。書籍「不調がデフォな私たちの背骨リセット」に詳細のチェック方法やエクササイズが載っていますので、これから小出しでご紹介していく予定です。
首肩こりと不定愁訴-運動と漢方によるアプローチ①-
2025年4月8日 12:30更新
専門外来コラム
首肩こりと不定愁訴-運動と漢方によるアプローチ①-
首肩こりは日本人の国民病とも言われています。スマートフォンの普及やデスクワーク・在宅ワークの増加により、首肩こりが当たり前のように感じている方も多くお見掛けします。首肩こりは私たちの日常生活を妨げる不快な症状ですが、それを発端にさまざまな不定愁訴が起こっているということは、あまり知られていないようです。気象病・自律神経失調症専門外来に来る患者さんは皆、強い首肩こり持ちです。しかし、自覚すらない場合が多く、頭痛やめまい、全身倦怠感、吐き気など他の症状を主訴として受診されています。首肩こりの対処法に関する情報が飛び交っているものの、何が正しいのか判断が付き兼ねることもあるのではないでしょうか。まずは首肩こりがどのようにして起きているのかを知って頂き、ご自身に合った解消法を見つけましょう。
- 首肩こりの正体は?
首肩こりの「こり(凝り)」というのは、特定の筋肉の使い過ぎや筋力不足などによって筋肉の過緊張が続き、血行が悪くなっている状態です。つまり、首肩こりは、首肩まわりの筋肉が血行不良になっているということです。そもそも首は5㎏前後の頭を支えており、元々大きな負荷がかかりやすい場所です。私たち現代人は、長時間うつむき姿勢をする生活が定着してしまいました。うつむき姿勢は首肩まわりの筋肉に大きな負担がかかるので、首肩こりに悩まされる人が多いのも当然と言えるでしょう。首肩まわりの血液の循環が悪くなっていると、その部分に酸素や栄養が十分に行き届かなくなります。それだけではなく、老廃物が溜まりやすく、痛みにつながります。
- 首肩こりを引き起こす要因5つ
[①不良姿勢・骨格のゆがみ]
姿勢が悪いと、首肩まわりの筋肉に過度の負荷がかかり続けることになります。デスクワークやスマホを触っている時の姿勢は、頭がやや下がり、それを首肩で支えている状態です。痛みや凝りを感じていない時でも、首肩にはかなりの負担がかかっています。
首や頭が前に出ている姿勢が続くと、首肩をつなぐ胸鎖乳突筋という筋肉が硬くなります。骨格が歪んでいてストレートネックや猫背などがある方は、本人はまっすぐに立っているつもりでも、すでに頭が前に出てしまっています。すると、首肩まわりの筋肉は常に負担がかかっていて休まる暇もありません。
[②筋力不足]
重い荷物を持ったときを想像してみてください。荷物を持つための筋肉に過度な緊張が加わり、腕が痛くなったり張ったりすることがあると思います。首肩も同じです。そもそも筋力が足りていないと使い過ぎの状態になり、筋肉が伸びた状態で固まってしまっています。いくらストレッチしてメンテナンスを頑張っている人でも、筋力が不足していると首肩こりがすぐに起きてしまうのです。首肩こりによる不調が起こりやすいのは、首が細く、なで肩、そして女性であることが多いのをご存じでしょうか。というのは、女性は本来男性よりも筋肉量が少ないので、筋力不足による首肩こりを引き起こしやすいということです。
[③運動不足・誤ったメンテナンス]
運動不足の人は体を積極的に動かす機会が無いため、首肩まわりだけでなく、体全体が凝り固まってしまっている場合が多いです。一方、運動習慣のある人はさまざまな筋肉を動かし、血液の循環も良くなるため、筋肉の凝り固まり加減が変わってきます。たとえば水泳は、水を押しのけるために腕全体を回したり動かしたりますよね。この動きは肩甲骨がよく動くので、首肩こり対策には良い動きです。
また、首肩こりの原因が筋力不足にあるにも関わらず、ストレッチしかできていない場合、ストレッチというメンテナンスでは不十分です。もしも「毎日欠かさずストレッチしているのに首肩こりが治らない!」という人は、ストレッチはできていても、姿勢を維持するための筋力が足りなかったり、体のバランスが悪かったりと他にも問題があり、メンテナンス方法がご自身に合っていないのかもしれません。
[④自律神経が乱れている・ストレス]
自律神経と首肩こりはお互いに影響し合っています。というのは、「自律神経が乱れる→首肩こりが起こる」「首肩こりが酷い→自律神経が乱れやすくなる」という双方向の関係です。せたがや内科の自律神経失調症専門外来には、頭痛やめまい、倦怠感など全身にさまざまな不調が出ており、ご自身で自覚ができないほどに首肩が凝っている患者さんが多くいらっしゃいます。ストレス等で自律神経が乱れて首肩が凝り、余計に自律神経が整えづらくなって負の連鎖が起こってしまうのです。そのような方は、首肩こりを改善するストレッチやエクササイズを実施すると不調も良くなることが多いです。
[⑤血行不良]
首肩こりの正体は首肩まわりの筋肉の血行不良ですが、そもそも体全体が血行不良に陥っていると、首肩こりを引き起こしやすい体質になります。血行不良の原因はさまざまですが、体が冷えていると冷えた血液が全身を巡り、循環も悪くなっていきます。特に首は露出していることが多く冷えやすい場所でもあるので、首を温めたりお風呂に入ることが有効です。血行不良は冷えだけでなく、ストレスや運動不足でも起こります。そのため、上記の5つは独立しているというよりかは、それぞれが影響し合っていると考えた方が良いでしょう。
- 治療の選択肢は漢方、ストレッチ、運動
一時的に血行不良を解消する方法はありますが、それでも慢性的に首肩こりに悩まされているという方は、生活習慣に問題があったり、骨格にゆがみが生じて改善しづらい体になっていたりする可能性があります。その場合は、首肩まわりを軽くストレッチするだけではメンテナンスが足りないかもしれません。根本的に治したいという方は、漢方薬の併用や、背骨全体のメンテナンスをする必要があります。(次回のコラムで詳しく書いていきます)
Blogメニュー
▶Blogトップ