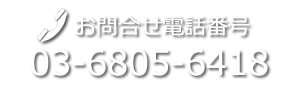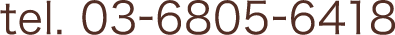自律神経に優しい環境づくりと夏でもできるセルフケアー
2025年8月7日 06:51更新
専門外来コラム
夏に気をつけたい自律神経の不調は?―自律神経に優しい環境づくりと夏でもできるセルフケアー
梅雨が明け、台風が通過しない限りは、気象病を気にせずに過ごせる期間に入りました。梅雨明け後は夏を楽しみたいところですが、最近の夏は35℃以上の高温、熱帯夜、湿度も高く、うだるような蒸し暑さが長期間続くようになりました。危険な暑さや熱中症警戒アラートのために外出を控える人も珍しくなくなり、室内で過ごす時間が増えていると思います。その結果、熱中症以外にも夏に起こりやすい不調や対策も変わってきており、私たちも日々アップデートしなければいけません。夏の過ごし方は秋の体調にも影響しますので、夏の体のメンテナンス法を身に付けましょう。
- 夏に気をつけたい自律神経の不調
[冷房病]
冷房病とは、冷房の効いた環境に長時間いることによってさまざまな不調が出ることを言います。正式な病名ではありませんが、夏の代表的な不調の一つです。冷房病で起こる不調は、自律神経や冷えによる血行不良が関係しています。症状は、冷え・むくみ、首肩こり、倦怠感、胃腸の冷え(食欲不振、腹痛、下痢など)、女性の場合は月経に影響が出ることもあります。最近では熱帯夜が続いているので夜間も冷房を付けっぱなしにする方が大半だと思いますが、冷房病の影響で朝から体がぐったりしていることもよく聞くお話です。
[夏の寒暖差疲労]
寒暖差疲労といえは春や秋のイメージですが、夏は室内外の気温差の影響が大きいです。寒暖差疲労というのは、私たちの体温調節を担当している自律神経が急激な温度差にうまく対応しきれず、疲労感、冷え、首肩こり、頭痛などさまざまな不調が起こることを言います。夏の場合は、冷房の効いた室内環境と35℃を超える外気を行き来すると、大きな温度差を体験することになります。すると、体温調節がうまくいかなくなり、自律神経が乱れて不調につながります。疲労感、倦怠感、頭痛、めまい、食欲不振、不眠、冷えやのぼせ、肌トラブルなどが主な症状です。自律神経の乱れ、血行不良が関係しているという点では冷房病と似ています。
[不眠]
近年の夏は熱帯夜が当たり前になっており、蒸し暑さによる不眠が起こりやすいです。私たちは眠っている間、大量の汗をかきます。夏は気温が高いだけでなく湿度も高いため、汗が蒸発しにくく、不快感や体温調節の不良が影響して睡眠の質を下げてしまいます。また、夏は活動的なイメージがあるかもしれませんが、1日中冷房の効いた部屋で過ごし、運動不足になる季節へと変化してきました。そのため、日中の活動不足で眠りづらくなっている現状もあるでしょう。
- 湿度が与える自律神経への影響は意外と大きい
[湿度と自律神経]
自律神経には体温調節を行う役割がありますが、湿度が高いとその機能が乱れやすく、交感神経が過剰に優位な状態になります。また、湿度が高いことで汗が蒸発しにくく、体温がうまく下がらないため、体に熱がこもります。すると、熱中症のような症状、頭痛、吐き気、ほてり、だるさなどが出やすいです。
[湿度と体感温度]
みなさんは湿度と体感温度の関係をご存じでしょうか。私たちの体は、湿度が高いと暑く感じ、湿度が低いと涼しく感じます。湿度が高いと汗が蒸発しにくくなるため、体が熱をうまく逃がすことができず、暑さを感じやすくなります。特に、湿度が70%以上になると体感温度が急激に上昇し、実際の気温より5℃以上も高く感じることもあります。反対に、湿度が低いと汗が蒸発しやすくなるため、体温が効率よく下がります。
・気温25℃ / 湿度60% → 体感温度は約27℃~28℃程度
・気温30℃ / 湿度80% → 体感温度は35℃以上に感じることも
・気温25℃ / 湿度40% → 体感温度は23℃~24℃程度に感じやすい
このように、湿度が高いと、私たちの体は気温以上に暑さを感じます。そのため、湿度をコントロールすることが快適な生活には不可欠です。
- 自律神経に優しい夏の過ごし方
[冷房病の対策]
冷房病対策のポイントは自律神経の乱れを防ぎ、冷えによる血行不良を避けることです。室温を26~28℃に設定し、強く冷やし過ぎないこと、そして直接風に当たらないことをお勧めします。冷え対策のグッズとしては、ひざ掛け、上着、ストール、レッグウォーマー、靴下(足首が隠れることが大切です)を活用すると良いでしょう。首・足首・手首、お腹には大きな血管が流れているため、この4点を守るようにすると冷えすぎるのを予防できます。また、飲みものはなるべく温かいものを飲み、夜は入浴で体の内側から温めると良いでしょう。
[寒暖差疲労の対策]
まずは寒暖差が起きにくい環境調整をしましょう。急な温度差が発生しないように、冷房の温度設定を低くし過ぎず、そして扇風機などの風を使って空気の流れを作ると良いと思います。寒暖差疲労に対してできることは、服装でも体温調節ができるように工夫すること、入浴で冷えのリセット、こまめな水分・ミネラル補給、睡眠の質の確保、軽い運動やストレッチ、深呼吸でリラックスなどです。
[湿度を考慮した環境調整]
適切な湿度調整をするだけでも、暑さによる不快感や自律神経の不調が起きにくくなります。まずはエアコンの除湿機能を使用して体感温度を下げる工夫をしてみましょう。夏は湿度50%を目安に、ご自身が快適と思える湿度を探してみてください。さらに、風通しが良いと湿度がこもりにくくなり、涼しさを感じることができます。サーキュレーターや扇風機を活用して空気の流れを作りましょう。また、夜は除湿器を活用しながら、通気性の良いシーツや寝具・冷感マットなども併せて使用することで、「涼しいけれど体が冷えない」と思う環境を探せると、不眠の解消につながると思います。
- 夏でも続けたい背骨の運動
夏は自律神経が乱れやすく、運動不足にも陥りやすいため、心身のメンテナンスが難しい季節になってきています。疲労の溜まる日々だからこそ、自分自身のメンテナンスは欠かしてはいけません。そこで、室内でもできる運動をご紹介します。
[ヨガ]
ヨガは呼吸法とストレッチを組み合わせた運動で、自律神経の調整に効果があります。初心者でも手軽に始めやすく、室内で行えるため、無理なく継続できます。ヨガのポイントは呼吸です。呼吸に集中することで、副交感神経が優位になり、リラックスすることができます。
[ピラティス]
ヨガと似ているようで異なるのがピラティスです。ピラティスは体幹を鍛える運動が多く、呼吸と筋肉を意識的に使うため、自律神経のバランスを整えるのに効果があります。背骨リセットの効果もあり、私は患者さんにもピラティスをお勧めしています。特に、背骨を意識して姿勢を正すことが多いため、日常生活の中での体の使い方にも良い影響を与えます。
[背骨リセット]
背骨は自律神経などの大切な神経の通り道です。背骨が歪んでいると自律神経が乱れる原因になり、夏の暑さにも耐えられなくなってしまいます。背骨のリセットは、体の中心軸を整え、姿勢の改善、筋肉の緊張緩和、体幹の強化、血行促進、内臓の調整、自律神経機能の活性化など、さまざまな効果があります。日々継続していくことで不調の起こりにくい体の土台を作ることができます。
前へ:« 気象病治療に効果のある五苓散の使い方
次へ:2025・9 気象病が女性に多い理由は?―自律神経や女性ホルモンとの関係― »
Blogメニュー
▶Blogトップ