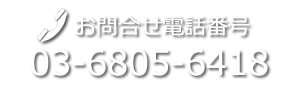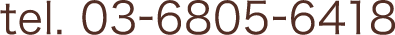寒暖差疲労対策~春に向けて実践したい運動~
2025年2月8日 14:16更新
専門外来コラム
寒暖差疲労対策~春に向けて実践したい運動~
1月下旬頃から、突然春のように気温が上がったり再び真冬の寒さに戻ったりと、寒暖差を肌で感じる日が多くなってきました。気象病や自律神経の乱れによる体調不良を抱えている人の中には、寒暖差による心身への影響が出はじめているのではないでしょうか?一般的には寒暖差は春・秋に注目されるイベントではありますが、年々寒暖差が気になる時期は長くなっているように思います。寒暖差による不調は低気圧によるものよりも少々自覚するのが難しく、対策も曖昧なところがありますが、生活の中で工夫すると過ごしやすくなるのは確かです。冬から春に向けて行いたい寒暖差対策についてご紹介します。
・寒暖差疲労は冬からスタート
最近の関東の気温の推移は、最低気温が0℃前後、日中10℃超えのパターンが多いです。この場合、1日の気温差が10℃近くになります。気温差が7~8℃以上になると寒暖差の影響を受けやすいとされているので、朝晩は厳しい冷え込み、日中はやや日差しを感じる暖かさとなり寒暖差を体感します。今年は年末年始にインフルエンザやコロナ・発熱を伴う風邪が大々的に流行したため免疫力や体力が弱っており、自律神経が乱れやすくなっている状態の人が多いでしょう。ご自身が想定していた以上に身体や心に負担がかかっていることがありますので寒暖差に負けないように対策をして頂きたいところです。
・トリプル寒暖差とは?
一時、「トリプル寒暖差」という言葉が注目されました。
▹1日の中での気温差
▹前日との気温差
▹室内外での寒暖差(家の中、電車の出入りなど)
トリプル寒暖差とは上記3つの寒暖差を指します。外気温が上下すると、それに適応するために自律神経が機能します。私たち人間の体温は一定に保たれているので、気温の変化に左右されずに一定の体温を保つため、気温差が大きいほど自律神経がたくさん働かなくてはなりません。1つの寒暖差だけでも体に負担がかかりますが、それがトリプルとなって積み重なると、とても不調の出やすい状況ができあがります。
・冬にやっておきたい寒暖差対策
[食事と睡眠で自律神経のベース作り]
2月は、年末年始の繁忙期を終えてやっと一息つくところでしょうか。冬の間に整えておきたいのが、規則正しい生活習慣です。基本的なことですが、その基本が自律神経の大切な土台を作ります。まずは食事と睡眠。食事は朝・昼・夜少しでも食べて体に規則正しいリズムを付けることから始めましょう。食べたり食べなかったりすると、血糖値の上下が激しくなり自律神経に負担がかかります。時間が無くて夜に食べ過ぎてしまうと消化にエネルギーが必要になり睡眠の質が落ちますので1回や2回にまとめて食べるのもお勧めできません。胃腸の調子を整えるためにはヨーグルトなどの乳酸菌、お米、カボチャ、豆や芋、食物繊維などを意識して食べると良いでしょう。
睡眠は自律神経を整え、心身の回復を図るために最も有効な方法です。今の季節は寒さや乾燥で睡眠が妨げられやすいです。眠る前(90分前がベストです)には入浴でしっかりと身体を温め、深部体温が下がるタイミングで寝床に入ると入眠しやすくなります。乾燥しすぎているようであれば加湿器を使用したり洗濯物を干したりして寝ると良いでしょう。また、寝床が冷たすぎると逆に身体が冷えすぎてしまうので、布団乾燥機などで少し温めておくと暑すぎず寒すぎず眠れると思います。
[寒暖差に合わせた服装調節]
冬の寒暖差で特徴的なのは、室内外・室内での寒暖差が大きくなることです。家の中と外だけにとどまらず、家の中では浴室やリビング、寝室などの気温差が大きく、行ったり来たりするだけで自律神経に負担がかかります。また、外では電車に乗る方は要注意です。駅のホームは外同様に寒いですが、電車の中は暖かくのぼせやすい環境です。寒さ対策として首が付く場所を守ることを推奨していますが、急に暖かい環境に出る時はマフラーなどを外すだけでも余計な体温が逃げやすくなります。服装の調節をするだけでも快適さが変わり、気分が悪くなったりするのを防げると思います。
・春に向けて実践したい運動
春に起こり得る気象病の症状として特徴的なのが倦怠感です。春は「寒さ→暖かさ」へと変わる時期であるため、副交感神経の働きが強く感じるようになります。ほどよく副交感神経優位だとリラックス状態なのですが、緊張が緩み過ぎてしまうと怠さや眠気が出てしまいます。また、外気の暖かさに対して体温が上がり過ぎないように、汗をかいて体温調整をする必要もあります。体を程よく緊張させ、そして汗をかく練習のためにも春に向けて運動を始めたいところです。
[まず浮腫みを取る]
冬の間、動くのが億劫で運動不足だった人は、全身がやや浮腫んでいる可能性があります。体に水分が溜まり過ぎていると、体温調節がしづらくなったり冷えやすくなったりして不調の原因になります。
浮腫みを取るには①ふくらはぎをストレッチ→②下半身を使う全身運動をお勧めします。ふくらはぎは“第二の心臓”と呼ばれていて、下半身に溜まった血液を心臓へと元に戻すポンプのような役割をしています。ふくらはぎが凝り固まって血行不良だったり筋力不足だったりすると、下半身に余分な水分が溜まりやすくなります。まずはふくらはぎや膝の裏あたりをテニスボールでゴロゴロ。ふくらはぎの動きを良くすると良いでしょう。次に全身運動です。簡単なものだとウォーキング、もう少し負荷をかけられるのであればジョギングや水泳などをすると全身の血流が良くなります。軽く汗をかく程度まで頑張れると、汗をかく練習にもなります。浮腫みが取れると体が軽くなったように感じると思いますので、春の倦怠感も予防できます。
[背骨のメンテナンスで自律神経を強くする]
背骨と自律神経には深く関係があります。自律神経の通り道をメンテナンスする癖を付けることで基盤をしっかりとしたり、キャパシティーを増やすことにつながります。特に首は自律神経にとって最も重要と言って良いほど大切な場所です。今回は首のケアから。賀来大樹さんとの共書籍「不調がデフォな私たちの背骨リセット」の中で患者さんに好評のエクササイズを紹介します。
・後頭下筋ほぐし(背骨リセットP24)
イスに座り、頭と首の境目の部分が刺激されるようにもたれかかります。20秒ほどを目安に行いましょう。
・モビライゼーション
後頭下筋をほぐしたら、足を腰幅に開いて立ち、腕を真横に大きく広げます。
左手と右手が交互に下になるように腕をひねりながら、同時に、首をひねって親指が上を向いている方の手の方を向きます。手は上・下、首は右・左、とリズムよく20秒続けましょう。
本来であれば一通りメニューをこなして頂きたいところですが、上記2つはその場で簡単にできるのではじめの一歩としてもお勧めです。首まわりが楽になり動きが改善されるので、頭痛やめまい・眼精疲労などの予防に役立ちます。首肩こりのエクササイズを行う時、腸腰筋(背骨と骨盤をつなげる筋肉)という筋肉のストレッチをしてから行うと、より効果が出ますので試してみてください。
前へ:« 2025・1コラム 入浴のすすめと冬のメンテナンス
次へ:自律神経が乱れやすい春の不調とメンタルケア »
Blogメニュー
▶Blogトップ